グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2013年09月09日
『翁草』(拙著)県立土屋文明記念文学館
県立土屋文明記念文学館
群馬町は、群馬県群馬郡群馬町である。県名、郡名、町名が同じというのは、日本の中でも珍しいのではないだろうか。平成の合併で高崎市と一緒になる可能性があり、その名は消えようとしているが、この町に平成七年になって、県立の立派な記念館が開館した。土屋文明記念文学館である。総工費は三十億円に近く、個人を記念して建てられた群馬県の文学館という趣旨としても破格の費用である。
記念館がある群馬町保渡田地区は、古墳群があることでも知られている。古代、この地に有力な豪族が住みついていた証拠である。しかも、同じ群馬町に国分という地区があり、国分寺があったことも知られている。奈良朝の頃は、このあたりが群馬、当時の呼び名では上毛(かみつけ)の中心地であったと考えられるのである。万葉集の秀でた研究者であり、斎藤茂吉と並ぶアララギ派の歌人土屋文明の生誕地が、その万葉の時代に栄えた地にあるということは興味深いことではある。
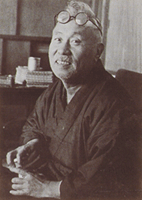
土屋文明は、長命で、平成二年に百歳を越えて亡くなっている。群馬の文学者として著名なのは、小説家では『田舎教師』などの作品で知られる田山花袋、詩人では萩原朔太郎であるが、土屋文明は、二人に近い時代の人ながら長命であったために、まだ歴史上の人物という感じがしない。今日まで、文明の歌集も読んだこともないし、文明の万葉の評論も目にしたことがないので、人物の詳細もほとんど知らなかった。むしろ、同じ群馬町に生れた、詩人、童話作家の山村暮鳥の存在が大きかった。土屋文明記念文学館に足を向けたのも山村暮鳥の展示の企画があったからである。
山村暮鳥の展示も時間をかけて見て廻ったが、初対面というべき土屋文明の人生とその作品に、思いを馳せられてしまった。館内で販売されていた『土屋文明私観』原一雄著(砂子屋書房)を読み、その思いはいっそう強くなり、読後感のようなものとして書き留めたいという気になった。その内容は、原一雄氏の本からの引用のようになるが、著者の土屋文明への敬愛と、人物理解、鋭い歌の鑑賞は誠に見事であって、いずれは文明の歌集を手にしたいという気持にもなった。
原一雄氏は、大正元年の生まれと書いてあるので、九十歳を越えている。現在、音楽センターや群馬の県立美術館建築に貢献し、群馬の文化活動の進展に寄与し、大きな足跡を残した井上房一郎の遺志を継ぎ、財団法人高崎哲学堂の理事長として活躍されている。高崎高校の同窓会長も歴任した名士でもある。
土屋文明は、明治二十三年(一八九〇年)に群馬郡上郊(かみさと)村に生れた。家は農家であったが、決して豊かではなかった。兄弟も多く、文明は親戚に預けられて育っている。嫁いでいたが子供のなかった伯母の家である。大事にされたが、感受性が強く、頭の良い文明少年は、何となくこの村での暮らしが息苦しかった。それは、文明の祖父が、犯罪者で北海道の監獄で刑死したことからくる村人の視線のためだった。
文明は、下を向きながら歩く少年であった。その視線の先には、名の知れない野草があり、異常なほどに植物への関心を持ち続ける素地になったと原氏は著書に書いている。小学校の時に「アララギ」を購読し始め、百歳の死の直前まで短歌を追い求め、万葉の歌の探究に生涯をかけた文明にとって、植物は自分の分身のようでもあった。
「泣き文ちゃん」というほどに、小さい時から人の悲しみへの感受性が強かったことも文明の性格のひとつであった。それは文明の優しさであったが、貧しさや村人の冷ややかな態度の重圧から這い上がってきた反骨精神も持ち合わせていた。
文明は、親からは経済的に無理と反対されたが、周囲の勧めもあり、高崎中学に入学する。当時中学に進学できる者は一握りであり、成績が優秀であったとしても財力のない家の子供が多かった。文明の状況も同じであった。
「僕は運が良かったのだ、本当に運が良かったのだ」
と、文明が周囲の人々に語ったように、人との出会いに恵まれ、経済的支援も受けて、最終学歴が小学校で終るはずが、第一高等学校から東京帝国大学まで進んでしまうのである。このことは、ただ運が良いという以上に優れた頭脳の持ち主であったことを証明している。東京帝国大学では、哲学科で心理学を専攻している。
土屋文明の人生最大の師は、伊藤左千夫であった。『野菊の墓』の作者である。伊藤左千夫は歌人でもあり、写生を歌の根本に置くことを提唱した正岡子規の「アララギ」派に属していた。同門には、島木赤彦や斎藤茂吉、中村憲吉らがいる。伊藤左千夫は、人格者であった。酪農をしながら文学の道を歩み、高崎中学を卒業した文明を、中学の恩師であった村上成之という人の紹介で引き取り、働きの場を提供したばかりか、第一高等学校の受験を支援したのである。
伊藤左千夫の助力で、第一高等学校に入学し、同期に芥川龍之介、山本有三、菊池寛、久米正雄、倉田百三といった文学史上に名を残した人物と知己を得ることが出来たのである。「僕は運が良かった」というのは、こうした出会いも含まれているに違いない。
伊藤左千夫は、文明が一高を卒業した、大正二年に五十歳で脳出血のために急死するのだが、文明は棺にすがり、一目もはばからず泣きじゃくったという。「泣き文ちゃん」にとって人生最大の悲しみの瞬間であった。
唯真(ただまこと)つひのよりどとなる教(おしえ)
いのちの限り吾はまねばむ
伊藤左千夫が人格者と言ったのは、優れた文学者というだけでなく、人格に深く響いて人の生き方に影響を与える教育者の資質を感じるからである。近代人には胡散臭くなっている「真心」を文明青年に身を持って示した人であった。『野菊の墓』の主人公の心のあり方は左千夫そのものだったということを文明が伝えている。
大正七年に二十八歳で結婚した文明は、島木赤彦の推薦によって教職に就く。いきなり、諏訪高等女学校の教頭として赴任する。その二年後には、校長になる。日本全国で一番若い校長であった。信州で七年間の教員生活を過ごし、その間教え子の中には、作家の平林たい子や、左翼運動で獄中死した伊藤千代子がいた。短歌の創作から離れ、女学校の教育に専念したが、文明にとっては不可解な突然の転任の人事に、教職を捨てる。そこから歌人としての人生が始まったといって良い。このあたりは、上州人、土屋文明の反骨精神である。芥川龍之介は、文明の第一歌集『ふゆくさ』を評して
「文明には、和御魂(にぎみたま)と荒御魂(あらみたま)が同居している」
という意味の言葉を寄せている。
信濃にて此の国の磯菜食ひたりき世に従わず背かぬ我等にて
という、六十七歳の時の歌に文明の処世観が表現されている。「世に従わず背かぬ」という言葉はなかなか普通の人の口からは出てこない。忍耐と反骨と正義が含まれている。
土屋文明の歌集は多いが、戦災で東京の青山の家を焼かれ、群馬県の吾妻町に疎開し、戦後六年間あまり農耕生活を送り、万葉集の研究に没頭する時期があった。土や、植物に触れられる環境は、万葉の歌を調べるのには実にふさわしいものであった。
ただ、故郷である群馬町を訪れることはほとんどなかった。吾妻町は、榛名山の北側にあり、南側に位置する群馬町からはそれほど遠く離れてはいない。
青き上に榛名をとはのまぼろしに出でて帰らぬ我のみにあらじ
この歌碑が、生地の保渡田の「やくし公園」に建てられているが、土屋文明にとって故郷は、懐かしい場所ではあったが、ゆかりの人々はあったとしても、足の向く地ではなかった。
「故郷は遠きにありて思うもの::」
と室生犀星が言った言葉と、どこか重なるものがあるのだろうか。
農家の後継ぎでなかった私の叔父は、人情もろく磊落な父と違い、繊細で、几帳面な性格の人であった。今日の国立感染症研究所の前身である国立伝染病研究所に勤務し、東京に定住し、冠婚葬祭以外は実家をほとんど訪ねて来ることはなかった。草津に別荘を持ちながら、途中寄るようなこともしなかった。父が入院するようになった晩年には、何度も見舞ったが、自分が癌と診断された後は、甥の結婚式に参列したのを最後に、親戚の見舞いを望まなかった。故郷に対する文明の心境から昨年亡くなった叔父のことがふと思い出された。田舎の風景は美しく、幼いときに見た風景でもあり、どことなく甘美で懐かしいものがあっても、そのとき体験する人間模様は人さまざまである。

文明は、歌碑を建てることを拒み続けたらしい。生地の歌碑だけは許したが、文明が亡くなる年の完成である。果たしてそのような文明にとって、この立派過ぎるほどの文学記念館を天国から彼はどのような心持で眺めているのだろうか。
群馬町は、群馬県群馬郡群馬町である。県名、郡名、町名が同じというのは、日本の中でも珍しいのではないだろうか。平成の合併で高崎市と一緒になる可能性があり、その名は消えようとしているが、この町に平成七年になって、県立の立派な記念館が開館した。土屋文明記念文学館である。総工費は三十億円に近く、個人を記念して建てられた群馬県の文学館という趣旨としても破格の費用である。
記念館がある群馬町保渡田地区は、古墳群があることでも知られている。古代、この地に有力な豪族が住みついていた証拠である。しかも、同じ群馬町に国分という地区があり、国分寺があったことも知られている。奈良朝の頃は、このあたりが群馬、当時の呼び名では上毛(かみつけ)の中心地であったと考えられるのである。万葉集の秀でた研究者であり、斎藤茂吉と並ぶアララギ派の歌人土屋文明の生誕地が、その万葉の時代に栄えた地にあるということは興味深いことではある。
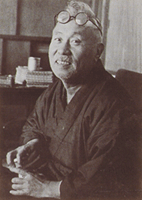
土屋文明は、長命で、平成二年に百歳を越えて亡くなっている。群馬の文学者として著名なのは、小説家では『田舎教師』などの作品で知られる田山花袋、詩人では萩原朔太郎であるが、土屋文明は、二人に近い時代の人ながら長命であったために、まだ歴史上の人物という感じがしない。今日まで、文明の歌集も読んだこともないし、文明の万葉の評論も目にしたことがないので、人物の詳細もほとんど知らなかった。むしろ、同じ群馬町に生れた、詩人、童話作家の山村暮鳥の存在が大きかった。土屋文明記念文学館に足を向けたのも山村暮鳥の展示の企画があったからである。
山村暮鳥の展示も時間をかけて見て廻ったが、初対面というべき土屋文明の人生とその作品に、思いを馳せられてしまった。館内で販売されていた『土屋文明私観』原一雄著(砂子屋書房)を読み、その思いはいっそう強くなり、読後感のようなものとして書き留めたいという気になった。その内容は、原一雄氏の本からの引用のようになるが、著者の土屋文明への敬愛と、人物理解、鋭い歌の鑑賞は誠に見事であって、いずれは文明の歌集を手にしたいという気持にもなった。
原一雄氏は、大正元年の生まれと書いてあるので、九十歳を越えている。現在、音楽センターや群馬の県立美術館建築に貢献し、群馬の文化活動の進展に寄与し、大きな足跡を残した井上房一郎の遺志を継ぎ、財団法人高崎哲学堂の理事長として活躍されている。高崎高校の同窓会長も歴任した名士でもある。
土屋文明は、明治二十三年(一八九〇年)に群馬郡上郊(かみさと)村に生れた。家は農家であったが、決して豊かではなかった。兄弟も多く、文明は親戚に預けられて育っている。嫁いでいたが子供のなかった伯母の家である。大事にされたが、感受性が強く、頭の良い文明少年は、何となくこの村での暮らしが息苦しかった。それは、文明の祖父が、犯罪者で北海道の監獄で刑死したことからくる村人の視線のためだった。
文明は、下を向きながら歩く少年であった。その視線の先には、名の知れない野草があり、異常なほどに植物への関心を持ち続ける素地になったと原氏は著書に書いている。小学校の時に「アララギ」を購読し始め、百歳の死の直前まで短歌を追い求め、万葉の歌の探究に生涯をかけた文明にとって、植物は自分の分身のようでもあった。
「泣き文ちゃん」というほどに、小さい時から人の悲しみへの感受性が強かったことも文明の性格のひとつであった。それは文明の優しさであったが、貧しさや村人の冷ややかな態度の重圧から這い上がってきた反骨精神も持ち合わせていた。
文明は、親からは経済的に無理と反対されたが、周囲の勧めもあり、高崎中学に入学する。当時中学に進学できる者は一握りであり、成績が優秀であったとしても財力のない家の子供が多かった。文明の状況も同じであった。
「僕は運が良かったのだ、本当に運が良かったのだ」
と、文明が周囲の人々に語ったように、人との出会いに恵まれ、経済的支援も受けて、最終学歴が小学校で終るはずが、第一高等学校から東京帝国大学まで進んでしまうのである。このことは、ただ運が良いという以上に優れた頭脳の持ち主であったことを証明している。東京帝国大学では、哲学科で心理学を専攻している。
土屋文明の人生最大の師は、伊藤左千夫であった。『野菊の墓』の作者である。伊藤左千夫は歌人でもあり、写生を歌の根本に置くことを提唱した正岡子規の「アララギ」派に属していた。同門には、島木赤彦や斎藤茂吉、中村憲吉らがいる。伊藤左千夫は、人格者であった。酪農をしながら文学の道を歩み、高崎中学を卒業した文明を、中学の恩師であった村上成之という人の紹介で引き取り、働きの場を提供したばかりか、第一高等学校の受験を支援したのである。
伊藤左千夫の助力で、第一高等学校に入学し、同期に芥川龍之介、山本有三、菊池寛、久米正雄、倉田百三といった文学史上に名を残した人物と知己を得ることが出来たのである。「僕は運が良かった」というのは、こうした出会いも含まれているに違いない。
伊藤左千夫は、文明が一高を卒業した、大正二年に五十歳で脳出血のために急死するのだが、文明は棺にすがり、一目もはばからず泣きじゃくったという。「泣き文ちゃん」にとって人生最大の悲しみの瞬間であった。
唯真(ただまこと)つひのよりどとなる教(おしえ)
いのちの限り吾はまねばむ
伊藤左千夫が人格者と言ったのは、優れた文学者というだけでなく、人格に深く響いて人の生き方に影響を与える教育者の資質を感じるからである。近代人には胡散臭くなっている「真心」を文明青年に身を持って示した人であった。『野菊の墓』の主人公の心のあり方は左千夫そのものだったということを文明が伝えている。
大正七年に二十八歳で結婚した文明は、島木赤彦の推薦によって教職に就く。いきなり、諏訪高等女学校の教頭として赴任する。その二年後には、校長になる。日本全国で一番若い校長であった。信州で七年間の教員生活を過ごし、その間教え子の中には、作家の平林たい子や、左翼運動で獄中死した伊藤千代子がいた。短歌の創作から離れ、女学校の教育に専念したが、文明にとっては不可解な突然の転任の人事に、教職を捨てる。そこから歌人としての人生が始まったといって良い。このあたりは、上州人、土屋文明の反骨精神である。芥川龍之介は、文明の第一歌集『ふゆくさ』を評して
「文明には、和御魂(にぎみたま)と荒御魂(あらみたま)が同居している」
という意味の言葉を寄せている。
信濃にて此の国の磯菜食ひたりき世に従わず背かぬ我等にて
という、六十七歳の時の歌に文明の処世観が表現されている。「世に従わず背かぬ」という言葉はなかなか普通の人の口からは出てこない。忍耐と反骨と正義が含まれている。
土屋文明の歌集は多いが、戦災で東京の青山の家を焼かれ、群馬県の吾妻町に疎開し、戦後六年間あまり農耕生活を送り、万葉集の研究に没頭する時期があった。土や、植物に触れられる環境は、万葉の歌を調べるのには実にふさわしいものであった。
ただ、故郷である群馬町を訪れることはほとんどなかった。吾妻町は、榛名山の北側にあり、南側に位置する群馬町からはそれほど遠く離れてはいない。
青き上に榛名をとはのまぼろしに出でて帰らぬ我のみにあらじ
この歌碑が、生地の保渡田の「やくし公園」に建てられているが、土屋文明にとって故郷は、懐かしい場所ではあったが、ゆかりの人々はあったとしても、足の向く地ではなかった。
「故郷は遠きにありて思うもの::」
と室生犀星が言った言葉と、どこか重なるものがあるのだろうか。
農家の後継ぎでなかった私の叔父は、人情もろく磊落な父と違い、繊細で、几帳面な性格の人であった。今日の国立感染症研究所の前身である国立伝染病研究所に勤務し、東京に定住し、冠婚葬祭以外は実家をほとんど訪ねて来ることはなかった。草津に別荘を持ちながら、途中寄るようなこともしなかった。父が入院するようになった晩年には、何度も見舞ったが、自分が癌と診断された後は、甥の結婚式に参列したのを最後に、親戚の見舞いを望まなかった。故郷に対する文明の心境から昨年亡くなった叔父のことがふと思い出された。田舎の風景は美しく、幼いときに見た風景でもあり、どことなく甘美で懐かしいものがあっても、そのとき体験する人間模様は人さまざまである。

文明は、歌碑を建てることを拒み続けたらしい。生地の歌碑だけは許したが、文明が亡くなる年の完成である。果たしてそのような文明にとって、この立派過ぎるほどの文学記念館を天国から彼はどのような心持で眺めているのだろうか。
2013年09月08日
『翁草『(拙著)濃尾平野、そして近江へ
濃尾平野、そして近江へ

大垣市は岐阜県、彦根市は滋賀県、犬山市は愛知県にある地方都市である。いずれもかつての城下町で、彦根城と犬山城は国宝である。戦国時代以降築かれた多くの城は、廃城となったものもあるが、武士の世の象徴として、江戸時代末までは、諸藩によって維持されてきた。火災によって焼失し、再建されたものもあるが、明治になって政府の方針で取り壊されたものが多い。さらに、第二次世界大戦のアメリカ軍による空襲で焼失してしまったものもある。国宝になっている城は、創建当時の姿が修復されながら残っている城で、今日では四城にしか過ぎない。他の二城は、兵庫県の姫路城と長野県の松本城である。
戦国の英雄、織田信長、豊臣秀吉を生んだ濃尾平野は広い。京の都にも近く、群雄割拠した戦国の世を制したのは、地理的条件が左右したことは否定できない。上杉謙信や武田信玄も有力大名ではあったが、京への距離が遠かった。そんなことを想いながら、城を見て廻った。
彦根城は、堀と石垣と櫓、そして天守のある小高い丘の調和が実に美しい。堀は、琵琶湖へ繋がっている。代々の藩主は井伊氏である。家康の家臣の中でも、井伊氏の武士団は屈強であったといわれている。幕末、井伊家から大老が出た。鎖国から開国を決断した井伊直弼である。安政の大獄を実行した人物で、吉田松陰や橋本左内らは処刑され、万延元年(一八六〇年)に水戸藩士らに桜田門外で暗殺された。三月三日、桃の節句にあたる日であったが雪が降っていた。享年四十六歳。その直弼が、十五年間過ごした埋木舎が、お堀の傍にある。修復中であったためか、しばらくは閉館するという立て札が掛けられ、見学することはできなかった。十四男であった直弼が藩主になる可能性は少なく、埋れ木と住まいを名づけたのもうなずける。今日、同名の茶菓子が名物になっている。少し高価なお菓子だが、抹茶にまぶされて上品な味がする。文化六年の創業というから伝統の味である。
犬山城は、別名白帝城ともいう。この城も小高い丘にあって、断崖の下を木曽川が流れている。天守はそれほど大きくはないが、木組みがりっぱである。つい最近まで、成瀬という人が所有していたというから驚きである。現在では、財団法人になって管理されている。個人であれば相続税がかけられるからであるが、平成までよく殿様の末裔とはいえ維持できたものだと感心した。城は、戦乱の世の象徴のようなものであるが、外面の美しさと、巨木を組み合わせた日本建築の様式を知ることができる。大垣城は、戦災で焼失したために、復原された城は鉄筋コンクリート造りで外観だけが往時の姿を偲ばせている。
 濃尾平野は、尾張と美濃にまたがる平野という意味である。犬山市はこの平野の外れにあるが、以前職場の同僚だった人が隣町に住んでいて、再会のついでに国宝犬山城と明治村を案内してもらうことにしたのである。大垣や、彦根は彼に会う前に足をのばしてみたのだが、大垣は、松尾芭蕉が『奥の細道』の結びの地としたところでもある。雪の山寺に次ぐ芭蕉ゆかりの地を訪ねるのもこの旅の目的のひとつであった。
濃尾平野は、尾張と美濃にまたがる平野という意味である。犬山市はこの平野の外れにあるが、以前職場の同僚だった人が隣町に住んでいて、再会のついでに国宝犬山城と明治村を案内してもらうことにしたのである。大垣や、彦根は彼に会う前に足をのばしてみたのだが、大垣は、松尾芭蕉が『奥の細道』の結びの地としたところでもある。雪の山寺に次ぐ芭蕉ゆかりの地を訪ねるのもこの旅の目的のひとつであった。
大垣駅からほど近い場所から粋な観光コースが整備されていた。駅構内にある観光案内所に立ち寄ると、地図を示しながら丁寧に係りの人が説明してくれた。深川から旅立った芭蕉が各所で作った俳句が二十句、船町港跡までの道すがら、適度の間隔で石碑に刻まれているのである。所用時間はゆっくり歩いて二十分位である。
最初の句碑は
行春や鳥啼き魚の目ハ泪
結びの句碑は
蛤のふたみに別行秋そ
である。行春と行秋が呼応していることがわかる。

紀行『奥の細道』は、実に入念に行程が練られ、構成もされている。行き当たりばったりの無計画な紀行文ではない。文学作品として追従を許さないものがある。卓上の想念だけで書かれていないからである。そして、全国に知己があったということも、芭蕉が厭世の人ではなかったこと教えている。芭蕉の門人には、武士もいたし富豪な商人もいた。大垣に芭蕉を迎えた谷木因は廻船問屋の経営者である。
谷木因は、門下というよりは芭蕉の友人のような人物であったらしい。気心が通じていたのか何度となく大垣に足を運んでいる。芭蕉は、旅の疲れをこの地で癒したが、伊勢へ旅立つのである。
蛤のふたみに別行秋そ
は、旅の終点に親しき人々との再会での結びの句ではありながら、新たな別離の句でもある。芭蕉の人生に対する無常観が表われている。無常というのは、はかなく寂しいという響きのある言葉ではなく、日々変化して同じ状況が続かないという意味で、自然界の法則そのものである。だから
人の世は無常というもその日々を真心尽す人に幸あれ
という生き方ができれば良いのだろう。時間は止まってくれないのである。
人は悲しい時も、辛い時もあるし、長く病気をすることもある。無常だから幸せな時へと変化し、健康にもなることができるのである。絶頂があれば奈落も経験する。
大垣の俳人の送別の句がある
秋の暮れ 行く先々は 苫屋哉 木因
霧晴れぬ 暫く岸に 立ち給へ 如行
職場の同僚だった人に再会する。同僚といっても、年齢は親子ほどの差がある。彼は今、働きながら大学院に通っている。卒論が提出した後ならば、というのでこの時期になった。名鉄犬山線の柏森という駅に近いアパートに住んでいる。夕方六時に会うことになっていたが、名鉄の新名古屋駅から間違って違う路線に乗ったために一時間以上も遅れてしまった。遅い夕食になって申し訳ないことをした。旅慣れているつもりだが、便利すぎる都会の地下鉄などは苦手である。アパートに泊めてもらい、翌朝は手作りのカレーまでごちそうになってしまった。郷里の群馬に帰って来た時は歓待しようと思っている。明治村には、彼の群馬ナンバーの車で行った。カーナビが付いている。
「これがないと、こちらではどうにもならない」とのこと。

明治村にはとりわけ見てみたい建物があった。アメリカの建築家、ライトが設計した帝国ホテルである。玄関部分だけが移築されて、客室などはない。東京にあった時の壮大な建物は見る機会がなかった。
外観からして異様な感じがする。まるで遺跡のような雰囲気がする。室内に入ってもその装飾された壁や柱に驚かされる。大谷石がふんだんに使われているのも特徴的である。建物の外部と内部が彫刻のようだと言ったら言い過ぎだろうか。あえて絵画や、彫刻作品を置く余地がない程、ライトの個性が空間を支配している。
ライトの設計した帝国ホテルが完成したのは、大正十二年であった。落成式典の日に、関東大震災が襲い、一部に被害は受けたが倒壊は免れた。耐震設計からすると、この建物は浮き基礎という工法がとられているのだという。そのことが、耐震性があったかという点では議論が分かれるところらしいが、建物は崩れず、多くの被災者の救護の場所にもなったという。
帝国ホテルは、一八九〇年(明治二十三年)に政府の発案と渋沢栄一や大倉喜八郎ら財界人が賛同して開業した国策ホテルだった。敷地も皇居に近い一等地であったことがそのことを物語っている。ライトの設計した帝国ホテルは、二代目になるが、設計者として別な人物が候補に挙がっていた。下田菊太郎という建築家であったが、彼は、明治の建築界で重鎮であった辰野金吾との確執により、一時日本を去りアメリカのシカゴで摩天楼建築といわれる大規模建築を手掛けていた。住宅建築家であり、小規模建築が中心であったライトよりもホテルの建築には適任者であったと言われていた。
辰野金吾は、東京駅の設計者としても知られているが、政治的にも権勢を持っていたらしい。イギリス建築家コンドルに学んだ人物である。赤坂離宮、帝国京都博物館、帝国奈良博物館の設計者として知られる、片山東熊らも同時代の設計者である。
建築家は、作品も個性的であるが、プライドも高いためか、弟子として働く時期はあっても、師と袂を分って独立するケースが多い。それはそれで悪いことではない。高崎の音楽センターや高崎哲学堂の設計をしたレーモンドは、ライトの弟子として帝国ホテルの設計に加わっている。
ライトが帝国ホテルの設計者となれたのは、林愛作という渋沢栄一や大倉喜八郎が抜擢した古美術商から支配人になった人物の縁であった。彼は、群馬県の出身で、アメリカに渡り成功を収めた人である。ホテル経営に経験はなかったが、アメリカの社交界に顔が広く、そこに集る人々のニーズが分っていたのを買われたのである。
建築費は当時の金額で百五十万円の予定であったが、建築が終ってみれば、その六倍にあたる九百万円を要した。しかも工期も送れ、落成式には林愛作は支配人の地位にはなかった。ライトも出席していない。落成式に建築の立役者が二人ともいないというのも奇妙であり、その日に大地震に見舞われたというあまりにも劇的な建物としてのスタートであった。
ライトの設計した帝国ホテルは、戦災にもあったが四十四年間その姿を東京内幸町に残した。しかし、多大な費用と芸術性に富んだ建物の寿命としては、決して長くない。暖房設備は電気であったためにコストがかかり、客室の居心地はそれほど客から評価されなかったらしい。なによりも、雨漏りが致命的であったという。デザインの主体となった大谷石が雨漏りの原因だったらしい。意匠ということばがあるが、ライトの天才はそこに発揮されたという人がある。一九九六年に開業した帝国ホテル大阪には、ライトのデザインが生かされている。明治村に移築されたのも、ライトの意匠の芸術性があったらばこそなのであろう。

大垣市は岐阜県、彦根市は滋賀県、犬山市は愛知県にある地方都市である。いずれもかつての城下町で、彦根城と犬山城は国宝である。戦国時代以降築かれた多くの城は、廃城となったものもあるが、武士の世の象徴として、江戸時代末までは、諸藩によって維持されてきた。火災によって焼失し、再建されたものもあるが、明治になって政府の方針で取り壊されたものが多い。さらに、第二次世界大戦のアメリカ軍による空襲で焼失してしまったものもある。国宝になっている城は、創建当時の姿が修復されながら残っている城で、今日では四城にしか過ぎない。他の二城は、兵庫県の姫路城と長野県の松本城である。
戦国の英雄、織田信長、豊臣秀吉を生んだ濃尾平野は広い。京の都にも近く、群雄割拠した戦国の世を制したのは、地理的条件が左右したことは否定できない。上杉謙信や武田信玄も有力大名ではあったが、京への距離が遠かった。そんなことを想いながら、城を見て廻った。
彦根城は、堀と石垣と櫓、そして天守のある小高い丘の調和が実に美しい。堀は、琵琶湖へ繋がっている。代々の藩主は井伊氏である。家康の家臣の中でも、井伊氏の武士団は屈強であったといわれている。幕末、井伊家から大老が出た。鎖国から開国を決断した井伊直弼である。安政の大獄を実行した人物で、吉田松陰や橋本左内らは処刑され、万延元年(一八六〇年)に水戸藩士らに桜田門外で暗殺された。三月三日、桃の節句にあたる日であったが雪が降っていた。享年四十六歳。その直弼が、十五年間過ごした埋木舎が、お堀の傍にある。修復中であったためか、しばらくは閉館するという立て札が掛けられ、見学することはできなかった。十四男であった直弼が藩主になる可能性は少なく、埋れ木と住まいを名づけたのもうなずける。今日、同名の茶菓子が名物になっている。少し高価なお菓子だが、抹茶にまぶされて上品な味がする。文化六年の創業というから伝統の味である。
犬山城は、別名白帝城ともいう。この城も小高い丘にあって、断崖の下を木曽川が流れている。天守はそれほど大きくはないが、木組みがりっぱである。つい最近まで、成瀬という人が所有していたというから驚きである。現在では、財団法人になって管理されている。個人であれば相続税がかけられるからであるが、平成までよく殿様の末裔とはいえ維持できたものだと感心した。城は、戦乱の世の象徴のようなものであるが、外面の美しさと、巨木を組み合わせた日本建築の様式を知ることができる。大垣城は、戦災で焼失したために、復原された城は鉄筋コンクリート造りで外観だけが往時の姿を偲ばせている。
 濃尾平野は、尾張と美濃にまたがる平野という意味である。犬山市はこの平野の外れにあるが、以前職場の同僚だった人が隣町に住んでいて、再会のついでに国宝犬山城と明治村を案内してもらうことにしたのである。大垣や、彦根は彼に会う前に足をのばしてみたのだが、大垣は、松尾芭蕉が『奥の細道』の結びの地としたところでもある。雪の山寺に次ぐ芭蕉ゆかりの地を訪ねるのもこの旅の目的のひとつであった。
濃尾平野は、尾張と美濃にまたがる平野という意味である。犬山市はこの平野の外れにあるが、以前職場の同僚だった人が隣町に住んでいて、再会のついでに国宝犬山城と明治村を案内してもらうことにしたのである。大垣や、彦根は彼に会う前に足をのばしてみたのだが、大垣は、松尾芭蕉が『奥の細道』の結びの地としたところでもある。雪の山寺に次ぐ芭蕉ゆかりの地を訪ねるのもこの旅の目的のひとつであった。大垣駅からほど近い場所から粋な観光コースが整備されていた。駅構内にある観光案内所に立ち寄ると、地図を示しながら丁寧に係りの人が説明してくれた。深川から旅立った芭蕉が各所で作った俳句が二十句、船町港跡までの道すがら、適度の間隔で石碑に刻まれているのである。所用時間はゆっくり歩いて二十分位である。
最初の句碑は
行春や鳥啼き魚の目ハ泪
結びの句碑は
蛤のふたみに別行秋そ
である。行春と行秋が呼応していることがわかる。

紀行『奥の細道』は、実に入念に行程が練られ、構成もされている。行き当たりばったりの無計画な紀行文ではない。文学作品として追従を許さないものがある。卓上の想念だけで書かれていないからである。そして、全国に知己があったということも、芭蕉が厭世の人ではなかったこと教えている。芭蕉の門人には、武士もいたし富豪な商人もいた。大垣に芭蕉を迎えた谷木因は廻船問屋の経営者である。
谷木因は、門下というよりは芭蕉の友人のような人物であったらしい。気心が通じていたのか何度となく大垣に足を運んでいる。芭蕉は、旅の疲れをこの地で癒したが、伊勢へ旅立つのである。
蛤のふたみに別行秋そ
は、旅の終点に親しき人々との再会での結びの句ではありながら、新たな別離の句でもある。芭蕉の人生に対する無常観が表われている。無常というのは、はかなく寂しいという響きのある言葉ではなく、日々変化して同じ状況が続かないという意味で、自然界の法則そのものである。だから
人の世は無常というもその日々を真心尽す人に幸あれ
という生き方ができれば良いのだろう。時間は止まってくれないのである。
人は悲しい時も、辛い時もあるし、長く病気をすることもある。無常だから幸せな時へと変化し、健康にもなることができるのである。絶頂があれば奈落も経験する。
大垣の俳人の送別の句がある
秋の暮れ 行く先々は 苫屋哉 木因
霧晴れぬ 暫く岸に 立ち給へ 如行
職場の同僚だった人に再会する。同僚といっても、年齢は親子ほどの差がある。彼は今、働きながら大学院に通っている。卒論が提出した後ならば、というのでこの時期になった。名鉄犬山線の柏森という駅に近いアパートに住んでいる。夕方六時に会うことになっていたが、名鉄の新名古屋駅から間違って違う路線に乗ったために一時間以上も遅れてしまった。遅い夕食になって申し訳ないことをした。旅慣れているつもりだが、便利すぎる都会の地下鉄などは苦手である。アパートに泊めてもらい、翌朝は手作りのカレーまでごちそうになってしまった。郷里の群馬に帰って来た時は歓待しようと思っている。明治村には、彼の群馬ナンバーの車で行った。カーナビが付いている。
「これがないと、こちらではどうにもならない」とのこと。

明治村にはとりわけ見てみたい建物があった。アメリカの建築家、ライトが設計した帝国ホテルである。玄関部分だけが移築されて、客室などはない。東京にあった時の壮大な建物は見る機会がなかった。
外観からして異様な感じがする。まるで遺跡のような雰囲気がする。室内に入ってもその装飾された壁や柱に驚かされる。大谷石がふんだんに使われているのも特徴的である。建物の外部と内部が彫刻のようだと言ったら言い過ぎだろうか。あえて絵画や、彫刻作品を置く余地がない程、ライトの個性が空間を支配している。
ライトの設計した帝国ホテルが完成したのは、大正十二年であった。落成式典の日に、関東大震災が襲い、一部に被害は受けたが倒壊は免れた。耐震設計からすると、この建物は浮き基礎という工法がとられているのだという。そのことが、耐震性があったかという点では議論が分かれるところらしいが、建物は崩れず、多くの被災者の救護の場所にもなったという。
帝国ホテルは、一八九〇年(明治二十三年)に政府の発案と渋沢栄一や大倉喜八郎ら財界人が賛同して開業した国策ホテルだった。敷地も皇居に近い一等地であったことがそのことを物語っている。ライトの設計した帝国ホテルは、二代目になるが、設計者として別な人物が候補に挙がっていた。下田菊太郎という建築家であったが、彼は、明治の建築界で重鎮であった辰野金吾との確執により、一時日本を去りアメリカのシカゴで摩天楼建築といわれる大規模建築を手掛けていた。住宅建築家であり、小規模建築が中心であったライトよりもホテルの建築には適任者であったと言われていた。
辰野金吾は、東京駅の設計者としても知られているが、政治的にも権勢を持っていたらしい。イギリス建築家コンドルに学んだ人物である。赤坂離宮、帝国京都博物館、帝国奈良博物館の設計者として知られる、片山東熊らも同時代の設計者である。
建築家は、作品も個性的であるが、プライドも高いためか、弟子として働く時期はあっても、師と袂を分って独立するケースが多い。それはそれで悪いことではない。高崎の音楽センターや高崎哲学堂の設計をしたレーモンドは、ライトの弟子として帝国ホテルの設計に加わっている。
ライトが帝国ホテルの設計者となれたのは、林愛作という渋沢栄一や大倉喜八郎が抜擢した古美術商から支配人になった人物の縁であった。彼は、群馬県の出身で、アメリカに渡り成功を収めた人である。ホテル経営に経験はなかったが、アメリカの社交界に顔が広く、そこに集る人々のニーズが分っていたのを買われたのである。
建築費は当時の金額で百五十万円の予定であったが、建築が終ってみれば、その六倍にあたる九百万円を要した。しかも工期も送れ、落成式には林愛作は支配人の地位にはなかった。ライトも出席していない。落成式に建築の立役者が二人ともいないというのも奇妙であり、その日に大地震に見舞われたというあまりにも劇的な建物としてのスタートであった。
ライトの設計した帝国ホテルは、戦災にもあったが四十四年間その姿を東京内幸町に残した。しかし、多大な費用と芸術性に富んだ建物の寿命としては、決して長くない。暖房設備は電気であったためにコストがかかり、客室の居心地はそれほど客から評価されなかったらしい。なによりも、雨漏りが致命的であったという。デザインの主体となった大谷石が雨漏りの原因だったらしい。意匠ということばがあるが、ライトの天才はそこに発揮されたという人がある。一九九六年に開業した帝国ホテル大阪には、ライトのデザインが生かされている。明治村に移築されたのも、ライトの意匠の芸術性があったらばこそなのであろう。
2013年09月07日
『翁草』(拙著)薄幸の女流文学者、その心性の清さ
薄幸の女流文学者、その心性の清さ
平成十七年一月十六日、東京は強風と氷雨の降る悪天候になっていた。銀座松屋で詩人金子みすず展が開かれていた。ある人から招待券をいただいていたこともあり、最終日の前日の日曜日、天気予報を無視しての東京行きとなった。
金子みすずは、童謡詩人として今日多くの人々に知られるようになったが、死後長くほとんど無名に近かった。彼女を世に出したのは、矢崎節夫という詩人である。彼が大学の一年生の時に、『日本童謡集』(岩波書店)で金子みすずの詩「大漁」に出会った。その感動と衝撃は矢崎の心から消えず、みすず探しが始まる。「大漁」の詩が掲載されたのは、西条八十の評価が高かったからである。
大漁
朝焼小焼だ
大漁だ。
大羽鰮の
大漁だ。
浜はまつりの
ようだけど
海のなかでは
何万の
鰮のとむらい、
するだろう。
七五調の響きが心地よい。それに加えて、命へのいたわり、それは人や動物にとどまらない。草花や自然界の無生物まで及んでいる。矢崎は、みすずが残した五百十二篇の手書きの詩が綴られた手帳を、みすずの死後五十数年になって、実弟から渡され、世に発表したのである。会場に展示されていたが、一九二五年、一九二六年(大正十四年、大正十五年・昭和元年)の数字が手帳に読み取れる。
金子みすずは、昭和四年に二十六歳で死んだ。自殺だった。離婚が引き金になったというが、ふさえという幼児を残しての死であった。他者を普通の人間以上に思いやれる心性の持ち主であったが、自己愛が希薄であったのだろうか。今日、いとも簡単に、しかも弱い者でも殺してしまう人間と比べてみると、なんとも対照的ではあるが、才能豊かな詩人の死は惜しい。
みすずの手帳は、もう一組清書したものが西条八十に渡されていたが、遺稿として出版されなかったのは不思議である。また、弟の上山雅輔は、作詞家、放送作家、脚本家、演出家として幅広く活躍した人物である。彼は、幼いときに親戚に養子に出され、みすずを実の姉と知らず、恋心を抱いたこともあったらしい。それはともかく、肉親としてみすずの詩の輝きがあまりにも近すぎて見えなかったのだろうか。
銀座松屋の八階の展示室には人があふれて、自筆の詩がゆっくりと見られなかったが、帰りがけに、展示の内容をまとめた本に目を通したとき、次の詩などはみすずらしいと思った。人も四季を何回か重ね、この世に生を受けた役割を終えて、また自然に戻っていくと考えるとなるほどと思う。ただ、風雪に耐えて、たくましく生きていく庭の寒梅も好きだ。新島襄の漢詩と比べてみたくなった。
木
お花が散って実が熟れて
その実が落ちて葉が落ちて
それから目が出て花が咲く
そうして何べんまわったら、この木は御用がすむかしら。
みすずの詩である。新島襄の寒梅の詩は、
寒梅
庭上の一寒梅
笑って風雪を侵して開く
争わず又力(つと)めず
自ら百花の魁を占(し)む

この日、金子みすずだけに会うのも、惜しいと考えて、樋口一葉女史を訪問したくなった。こちらは展示会を見に行ったわけではない。台東区に樋口一葉記念館がある。上野から北千住方面行きの地下鉄日比谷線の三の輪駅からほど近い場所にある。樋口一葉は、生涯十五回住まいを変えている。全てが東京であるが、十四回目の場所がこの地であった。ここで雑貨商を営んだ。近くには吉原遊郭があった。この町に暮らす人々の生き様を深く観察し、家長として母や妹の暮らしを支え、貧しい中に必死に生きた自分を投影させながら小説を書いた人である。
「奇跡の十四カ月」という期間に、今日樋口一葉の代表作と言われている作品は書かれたのである。みな短編小説になっているが、奇跡という意味には、短い期間というだけではなく、結核を患いながらの執筆であったからである。そして、わずか二十四歳の人生であった。
キリストの生涯を連想した。聖書には、キリストが宣教を始めたのは、およそ三十歳のときであったとしるされている。それから、数年後に十字架にかけられるのだが、福音書の記者は、その間の経緯に多くのページをさいている。そして、その間の空間的、時間的凝縮度の高さは、後の人類への贈り物になっている。誕生のいきさつの記述や少年期のエピソードは、十字架へ向かうイエスの悲壮な晩年の歩みを、称えるための添え物のように感じる。大胆な言い方をすれば、この「奇跡の数年間」は、イスラエルの民族の歴史の結晶のように思うのである。釈尊のような解脱したとされる宗教者も、個人だけの資質にのみに生まれるのではないと考えて見たくなった。ただ、個人史の中に、「奇跡の時間」を準備してきた蓄積を無視はできない。キリストが、聡明で多くの知識を学んでいたことも事実であり、樋口一葉の成績は、首席になるほどで、多くの書物を図書館に通い読み耽ることがあった。良き種のことを考えれば良い。

「奇跡の十四カ月」に書かれた代表作は『にごりえ』、『十三夜』、『たけくらべ』、『おおつごもり』などであるが、新潮文庫を買って読んでみたが、文語体でかなり平成人には難解である。『たけくらべ』は、映画などで大方の雰囲気とあらすじは覚えていたが、二、三度読み返してはみた。
『十三夜』は、樋口一葉の時代にありそうな話で、大衆の共感を得たかもしれない。生活のための結婚は、女性に耐え忍ぶ心を強要し、反対に心の自由を奪ったことになる。
一葉は、結婚はしなかったが、借金で身を売るぎりぎりの生活をした。幸か不幸か結核が彼女の命を奪った。
新渡戸稲造に代わり樋口一葉が、新しい五千円札の顔となったのは、お金に困っていた彼女には皮肉な出来事である。樋口一葉記念館には、福井日銀総裁から記念館の館長に番号の少ない新札が寄贈されている写真と、現物が展示されていた。

一葉の小説の題名が独特である。『たけくらべ』は「背比べ」のことだと思うし、『おおつごもり』は「大晦日」のことである。『十三夜』もよくわかる。『にごりえ』が良くわからない。「濁り江」ということばはあるが、果たしてその意味なのであろうか。
薄幸の女流文学者というタイトルが良かったかどうか。年若くして死んだからと言って不仕合わせとも言えない。さらにみすずの心性は清らかと言えるように思うが、一葉の場合は、理知的で生きるための借金を親しい人間以外にもする逞しさがあった。ただ、森鴎外が彼女の小説を絶賛したのはなぜかと考えてみたい。川端康成のような女流作家好きというわけでもないだろう。

樋口一葉同様、若き女手により家人を支え、真摯に短い生涯を終えた女流歌人がいた。「昭和の女啄木」と呼んだ人もいる。群馬県武尊山の麓、川場村の江口きちである。父親は、博打好きで妻子を置き去りに放浪し、母親は、きちが成人する前に脳溢血で死んだ。幼い妹と、五歳の時に脳膜炎により重い障害持った兄が残された。しばらくすると、廃人同様になって父親が帰ってきた。
きちは、母親の家業を継いだが、商売向きな性格ではなかった。それでも、妹が尋常小学校を卒業し、美容師の奉公ができるまで家計を支え、河井酔茗という歌人を師として歌を詠み続けていた。しかし、二十六歳の時、生活苦から逃れるように、白装束に身を整え、不自由な兄の行く末も心配し、枕を並べて服毒死したのである。昭和十三年十二月二日のことである。古い校舎を残し歴史民族資料館にしたその一画に、江口きちの遺品が展示されている。
辞世になった歌は
睡(ね)たらひて夜は明けにけりうつそみに聴きをさめなる雀鳴き初む
おおいなるこの寂けさや天地の時刻あやまたず夜は明けにけり
「貧乏は罪悪である」と言った友人がいるが、お金の苦労は決して心のゆとりを生まない。しかし、精神的に貧困になるということにはならない。死の間際にも、天地の摂理を聴き分けられた、若くして逝った江口きちの最後も悲しく惜しい。
2013年09月06日
『翁草』(拙著)山寺へ
 山寺へ
山寺へ二十一世紀に入り、今回が四回目の元旦東北行きとなった。東日本旅客鉄道発行の「正月パス」という切符を利用しての旅だが、有効期間は一月一日限りである。新幹線のグリーン席は別料金が必要になるが、指定席が四回とれる。北海道の函館の日帰りも可能である。利用する人が多くなったのだろう。JR東日本は強気になって、今年からは、一万二千円に値上げした。二割増でも遠距離を目的地にすれば、通常料金よりは、はるかに安い。民営化になって、様々な企画がなされるようになった。結構な事である。「青春18切符」などというのもある。在来線の普通列車に五日間乗り放題、一万一千五百円。時間のある高齢者なら、ゆったりとした楽しい旅ができるかもしれない。ネーミングも粋である。JRの宣伝のつもりではないからこれくらいに留めておきたい。
今年の目的地は、山形市郊外にある山寺にした。同じ榛名町に住む友人の提案でそうなった。目的地をどうしようかと考えていたところ
「一緒に行きましょうよ」
ということになった。彼のご子息は、東北大学の医学部に学んでいる。自慢の息子さんである。他に候補地にしていたのは、松島と平泉だったが、結果的には山寺で正解だったかもしれない。
大晦日に雪が降り、安中榛名駅までは、息子の車に乗せてもらうことにした。土産は奮発しないといけない。旅先から携帯電話で注文をとって、帰りの運転も頼むことができた。路が凍結していて、女性の運転手というわけにはいかない。
山寺が正解だったというのは、雪と関係がある。水墨画のような山寺を見ることが出来たし、雪のためか初詣の客も意外と少なく、芭蕉が「山寺は、とりわけ清閑の地である」という雰囲気を味わうことができたからである。平泉の中尊寺あたりを訪ねていたら人出が多く、都会の雑踏の中にいる気分になったに違いない。今年のNHK大河ドラマは「義経」である。
『春の雲』、『夏の海』、『秋の風』、『冬の渚』と紀行文を書き、一区切りしたという気持は強い。失礼ながらに謹呈した友人知己諸氏にも、暫くは充電してからにしたいと申し上げたが、人生という旅は続いている。暮れになって、近年来の旅行症が生じてきて、紀行文を書き続ける気分になった。
深川の庵から、旅から戻って二年もしない年の暮れに、白河の関を越えたくなり、なにかに憑かれたかのようにじっとしていられなくなった芭蕉ほどではないにしても、この性癖は死ぬまで直りそうもない。
本を渡される方からしたらご迷惑に違いないから、紀行文は書き溜めて置いても、しばらくは発行しないでおこうとも考えている。芭蕉の『奥の細道』も旅が終って、五年後に出版されている。推敲に推敲を重ねて世に問う程の真剣さと器量はないから、そのような大それた野心があるわけではない。ただ、テーマと本の名前は決めておこうと思う。『翁への道』という書名にした。翁とは、もちろん芭蕉を指しているが、これから年を重ねていくであろう自分自身のことでもある。旅先は、芭蕉ゆかりの地であることも意識したいし、そうした旅を重ねながら芭蕉という人の人生観を少しでも理解したいという意味も含まれている。
芭蕉を慕い、その足跡を辿りつつ本を書いた作家や俳人は数多い。それほどに、日本人にとって芭蕉は魅力的な人物である。既に読んだ作品の中でも、俳人の加藤楸邨の『芭蕉の山河―おくのほそ道私記』(読売新聞社)、『月山』で芥川賞を晩年近くに受賞した作家、森敦の『われもまた おくのほそ道』(日本放送出版協会)は、自分の体重をかけて書いている雰囲気のある好著である。体重をかけていると言ったのは、読者の意識に迎合するような書き方ではないというほどの意味である。二人の著名な先人の足元には及びもしないが、『翁への道』も全体重をかけて書くようにしたい。そのためには、芭蕉の句にさらに多く触れてみなくてはならない。加えて自分の心の識を高めなければならないが、後者の方が数十倍大変なことである。
東北新幹線から山形新幹線となり、板谷峠に向う山間の風景は雪景色である。雪も降っている。昨年の元旦とは違う雪国山形となった。上杉鷹山の米沢、温泉地と歌人斎藤茂吉で知られる上山のあたりも一面の銀世界であった。山形駅の改札の出口には、同志社大学時代の友人が出迎えてくれていた。年賀状のやりとりは続けていたが、会うのは三十年ぶりである。出かける前に電話したのだが、奥さんが出て
「何しろ三十年ぶりなので顔がわかるでしょうか。ところで、髪の毛なんか薄くなったりしていて」
と失礼なことを聞いてしまった。五〇代になった友人の髪は健在であった。そのことを彼に話すと
「それは、あなたのことでしょうよ」
と逆襲されてしまった。
ただ会って、話をしてみるといっぺんに記憶が蘇って来るから不思議である。駅構内の店でコーヒーを飲みながら話すと、立て板に水のように話が途切れない。同行の友人に申し訳ないようである。仕事のこと、家族のこと。驚いたのは、会社では英語を日常話して仕事をしているのだという。会社が外資系で、社長もアメリカ人。従業員も外国人が多いからだという。
「文法などは、あまり気にしないでサ。ブロークンイングリッシュというやつかな。初めは、ヒアリングができなくて困ったけれど、離すのか持っているかのどちらかを指示されたとき、間違えば大変なことになる場面があったが、そういうときは、不思議と理解できるものだヨ」
標準語でしゃべっているが、山形弁の訛りである。でもこうした言い方も失礼ではある。大学時代の印象は、どこかナイーブな印象があった。今の彼の言動はエネルギッシュそのものである。ただ、親切な人ということでは、昔も今も変わっていない。
駅に近い山形市内で電気店を経営していたが、先年お父さんが他界し、十数年前からサラリーマン生活である。会社は米沢市にあるという。
「今、もう一度心理学の勉強をしたいと本当に思っている。少し時代が早すぎたのかな」
と、現在の仕事に大学時代に専攻した学問を生かせていないことが残念そうである。
山寺には、彼の自家用車で行くことになった。市内見学のガイドもしてくれた。有名な芋煮会の大鍋のある場所にも案内してくれた。蔵王から発する馬見ヶ崎川の河岸を通る国道の脇に置かれている。

山寺の正式な名称は、宝珠山立石寺といい、貞観二年(西暦八六〇年)に慈覚大師(円仁)によって開山された、比叡山延暦寺の別院である。根本中堂もある。山全体に堂や坊があって、奥の院まで行くには千余段の石段を登らなければならない。
慈覚大師は、伝教大師、最澄の弟子で、天台宗第三代座主である。俗名を円仁といった。遣唐使として中国大陸に渡り天台宗を学んだ。『入唐求法巡礼行記』は、自作の旅行記として評価が高い。下野(現在の栃木県)の生まれで、東北地方の寺院の建立に力を尽くした。平泉の中尊寺や毛越寺も慈覚大師ゆかりの寺である。大師という称号は、朝廷からのもので僧侶の中で歴史上何人もいない。
山寺芭蕉記念館は元旦で閉館になっていたが、「風雅の国」で軽い食事ができた。仙山線の山寺駅側にあって、高台であるため、山寺の全体を見ることができる。水墨画のような風景はこの場所から見ることができたのである。まさに山寺であった。
松尾芭蕉がこの地を訪れたのは、元禄二年の七月十三日の午後三時頃であった。尾花沢に泊まり、その地の人々に勧められて朝早く出かけることになったのである。予定のコースにはなかったのである。この勧めを断っていたら名句
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
は生れなかったわけである。
芭蕉は推敲の人と言って良いくらい、何度も何度も句を練り直している、蝉の句も例外ではない。最初は
山寺や 石にしみつく 蝉の声
それが
さびしさや 岩にしみ込 蝉のこゑ
となり、『奥の細道』の中に配置されたときには
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
となったのである。デッサンから完成した画に至るまでの画家の作業にも似ている。芭蕉は、自分の心にピタッとはまるまでは推敲を止めなかったのである。練りに練るということは辛い作業に違いない。しかし、完成した時の喜びは大きい。
寺の前の店に駐車して、参拝することにしたのは良いが、石段は雪で覆われ、しかも踏み固められている。気を許せば滑って転倒する。芭蕉がこの石段を登ったのは夏である。四〇代半ばの杖が手放せない当時では初老の芭蕉と比べても条件が遥かに悪い。同行してくれた友人は曽良ではないが、山登りの愛好家ということもあり
「せっかく山寺に来たのだから登りましょうよ」
と先頭をきって登り始めた。案内人の山形の友人は、電気店を営んでいた頃、電気器具を背負ってこの石段を何度も登ったことがあるらしい。それでも当時は若かったに違いないから苦にはならなかったであろう。蝉塚のある所までということで、ゆっくり登ったのだが、手摺につかまったらかえって滑りやすいことに気づいた。見かねた山形の友人は
「カメラを持ってあげるよ。それにしてもこれでは、岩にしみいるは、凍みいると変えなければならないね」
と上手いことを言う。
閑けさや 岩に凍み入 靴の音
酔狂で句は作って見たが川柳にもなっていない。
結局、蝉塚を通りすぎて、仁王門まで登ったが、帰りは手摺にしがみ付きながら、上りの倍近くの時間がかかってしまった。

車を駐車していた店で、そばを食べることにしたが、石段のぼりのおかげで実に美味かった。名物の「力こんにゃく」も醤油味がしみて格別な味がした。『翁への道』の起点になった山寺行きは、前途の険しさを思い知らされるものがある。ただ、友人との再会は心に残るものが多かった。息子さんの受験が済んだら、家族連れで群馬に来てもらい、ゆっくり温泉にでも浸かってもらいたいと心底思った。
山寺の紹介は芭蕉に任せたい。
「山形領に立石寺と云山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊清閑の地也。一見すべきよし、人々のすゝむるに依て、尾花沢よりとつて返し、其間七里ばかり也。日いまだ暮ず。梺の坊に宿かり置て、山上の堂にのぼる。岩に巌を重て山とし、松柏年旧、土石老て苔滑に、岩上の院々扉を閉て、物の音きこえず。岸をめぐり、岩を這て、仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行のみおぼゆ。
閑さや岩にしみ入蝉の声」
尾花沢から山寺まで二十八キロを歩き、その足で石段を登った芭蕉の健脚には脱帽する。「山上の堂」とは、どのあたりまでだったのであろうか。蝉の種類は、何であったかという後世の論争より、余程興味を抱いた。
2013年09月04日
企画展「堀越二郎の軌跡』藤岡市歴史館
企画展「堀越二郎の軌跡』藤岡市歴史館

先週の日曜日、映画「風立ちぬ」のモデルになった、ゼロ戦の設計者堀越二郎の企画展を見に行った。藤岡の歴史資料館は既になく、新しくこの歴史館が建てられたとのこと。激しい雷雨の中ようやくたどり着くことができた。来館者は多く、それほど広くない館内は、人で溢れている。
堀越二郎が藤岡の出身だとは知らなかった。藤岡中学校から、第一高等学校、東京帝国大学に進んだ秀才だった。頭脳の優秀さはもちろんだが、非常に几帳面で、当時では珍しいゴルフが趣味だったようだ。その研究熱心さも紹介されている。文庫本が2冊販売されていたので購入、『零戦』堀越二郎著、『風立ちぬ』堀辰雄。『零戦』は読了。戦闘機とはいえ、よく短期間にこれほどの飛行機を設計できたことが驚きである。しかも、零戦はその形自身が美しい。繰り返し行われた試験飛行を見て、設計者の堀越も「美しい」とつぶやいたらしい。館内の廊下を歩いていたら、和算の大家関孝和の紹介があった。関孝和も藤岡の出身である。数学の偉人が生まれた地から、航空工学の秀才が生まれたことも無関係とは言えない。

先週の日曜日、映画「風立ちぬ」のモデルになった、ゼロ戦の設計者堀越二郎の企画展を見に行った。藤岡の歴史資料館は既になく、新しくこの歴史館が建てられたとのこと。激しい雷雨の中ようやくたどり着くことができた。来館者は多く、それほど広くない館内は、人で溢れている。
堀越二郎が藤岡の出身だとは知らなかった。藤岡中学校から、第一高等学校、東京帝国大学に進んだ秀才だった。頭脳の優秀さはもちろんだが、非常に几帳面で、当時では珍しいゴルフが趣味だったようだ。その研究熱心さも紹介されている。文庫本が2冊販売されていたので購入、『零戦』堀越二郎著、『風立ちぬ』堀辰雄。『零戦』は読了。戦闘機とはいえ、よく短期間にこれほどの飛行機を設計できたことが驚きである。しかも、零戦はその形自身が美しい。繰り返し行われた試験飛行を見て、設計者の堀越も「美しい」とつぶやいたらしい。館内の廊下を歩いていたら、和算の大家関孝和の紹介があった。関孝和も藤岡の出身である。数学の偉人が生まれた地から、航空工学の秀才が生まれたことも無関係とは言えない。
2013年09月01日
『冬の渚』(拙著)後記
後記
紀行文を書き始めてから四年が過ぎた。どうやら四巻となり、冬まで辿り着くことができた。春は雲を追い、夏は海を眺め、秋の風に吹かれ、冬はまた海のある浜辺にきてしまった。
紀行文の最後を『冬の渚』としたのには理由がある。二十四歳の冬、数学者の岡潔博士にお会いする機会があり、それ以来人生の師として今日まで生きてきた。余りにも師は高い峰であるために、頂きは見えてはいない。ただ登ろうという気持だけは忘れてはいない。
その岡先生に、作家の井上靖は
「岡さん。良い詩を教えてさしあげましょう」
と言って、示したのが三好達治の詩であった。
「日本よ、海の中には母がいる。フランスよ、母の中には海がある」
と簡略して、岡先生は、著書の中に引用されているが、フランスに留学され、日本を愛した先生にとって忘れ難い詩であったに違いない。ちなみにフランス語では、母も、海もメールである。
蛇足かも知れないが、三好達治のこの詩は、短いので全文紹介したい。
郷愁
蝶(てふ)のような私(わたし)の郷愁(きょうしゅう)!::。蝶はいくつか籬(まがき)を越え、午後の街角(まちかど)に海を見る::。私は壁に海を聴(き)く::。私は本を閉(と)じる。私は壁に凭(もた)れる。隣りの部屋で二時が打つ。
「海、遠い海よ!と私は紙にしたためる。―海よ、僕らの使う文字(もんじ)では、お前の中(なか)に母がゐる。そして母(はは)よ、仏蘭(フランス)西人(じん)の言葉では、あなたの中(なか)に海がある。」
海は人類にとっては故郷のような場所である。母の胎内も海の成分に似ている。海と陸地の境が渚である。海に発生したとされる生物が、海から陸に進出する時、多くの時間辛い進化の過程があった事を想像する。故郷を去ることにより、人々は自分を鍛えつつも、やがて母性に似た懐かしいその場所に戻ろうとする。
生後間もなく母と死別し、城を出て王子の身分を棄てた釈迦は、晩年北へ旅に出る。北は、母親の眠る故郷の地であった。涅槃に入った時、釈迦の頭は北に向き、西方見つめていた。良寛は、母の死後故郷に帰り、世俗とはかけ離れた中で仏の道を歩んだ。出雲崎の良寛堂にある、良寛像は、母の生地である佐渡島を見つめていた。直ぐ前は、浜辺である。
紀行の最後の地は、日本海が良いと思っていた。ならば、まだ一度も訪ねていない日本三景の一つ、天橋立が良いかと思っていたが、良寛の故郷越後で良かったかも知れない。冬の渚ではなかったが、タイトルの主旨からは離れていない。
弥彦山 佐渡の島影 秋津飛ぶ
紀行文を書き始めてから四年が過ぎた。どうやら四巻となり、冬まで辿り着くことができた。春は雲を追い、夏は海を眺め、秋の風に吹かれ、冬はまた海のある浜辺にきてしまった。
紀行文の最後を『冬の渚』としたのには理由がある。二十四歳の冬、数学者の岡潔博士にお会いする機会があり、それ以来人生の師として今日まで生きてきた。余りにも師は高い峰であるために、頂きは見えてはいない。ただ登ろうという気持だけは忘れてはいない。
その岡先生に、作家の井上靖は
「岡さん。良い詩を教えてさしあげましょう」
と言って、示したのが三好達治の詩であった。
「日本よ、海の中には母がいる。フランスよ、母の中には海がある」
と簡略して、岡先生は、著書の中に引用されているが、フランスに留学され、日本を愛した先生にとって忘れ難い詩であったに違いない。ちなみにフランス語では、母も、海もメールである。
蛇足かも知れないが、三好達治のこの詩は、短いので全文紹介したい。
郷愁
蝶(てふ)のような私(わたし)の郷愁(きょうしゅう)!::。蝶はいくつか籬(まがき)を越え、午後の街角(まちかど)に海を見る::。私は壁に海を聴(き)く::。私は本を閉(と)じる。私は壁に凭(もた)れる。隣りの部屋で二時が打つ。
「海、遠い海よ!と私は紙にしたためる。―海よ、僕らの使う文字(もんじ)では、お前の中(なか)に母がゐる。そして母(はは)よ、仏蘭(フランス)西人(じん)の言葉では、あなたの中(なか)に海がある。」
海は人類にとっては故郷のような場所である。母の胎内も海の成分に似ている。海と陸地の境が渚である。海に発生したとされる生物が、海から陸に進出する時、多くの時間辛い進化の過程があった事を想像する。故郷を去ることにより、人々は自分を鍛えつつも、やがて母性に似た懐かしいその場所に戻ろうとする。
生後間もなく母と死別し、城を出て王子の身分を棄てた釈迦は、晩年北へ旅に出る。北は、母親の眠る故郷の地であった。涅槃に入った時、釈迦の頭は北に向き、西方見つめていた。良寛は、母の死後故郷に帰り、世俗とはかけ離れた中で仏の道を歩んだ。出雲崎の良寛堂にある、良寛像は、母の生地である佐渡島を見つめていた。直ぐ前は、浜辺である。
紀行の最後の地は、日本海が良いと思っていた。ならば、まだ一度も訪ねていない日本三景の一つ、天橋立が良いかと思っていたが、良寛の故郷越後で良かったかも知れない。冬の渚ではなかったが、タイトルの主旨からは離れていない。
弥彦山 佐渡の島影 秋津飛ぶ


