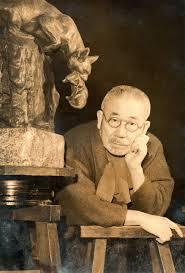2013年09月06日
『翁草』(拙著)山寺へ
 山寺へ
山寺へ二十一世紀に入り、今回が四回目の元旦東北行きとなった。東日本旅客鉄道発行の「正月パス」という切符を利用しての旅だが、有効期間は一月一日限りである。新幹線のグリーン席は別料金が必要になるが、指定席が四回とれる。北海道の函館の日帰りも可能である。利用する人が多くなったのだろう。JR東日本は強気になって、今年からは、一万二千円に値上げした。二割増でも遠距離を目的地にすれば、通常料金よりは、はるかに安い。民営化になって、様々な企画がなされるようになった。結構な事である。「青春18切符」などというのもある。在来線の普通列車に五日間乗り放題、一万一千五百円。時間のある高齢者なら、ゆったりとした楽しい旅ができるかもしれない。ネーミングも粋である。JRの宣伝のつもりではないからこれくらいに留めておきたい。
今年の目的地は、山形市郊外にある山寺にした。同じ榛名町に住む友人の提案でそうなった。目的地をどうしようかと考えていたところ
「一緒に行きましょうよ」
ということになった。彼のご子息は、東北大学の医学部に学んでいる。自慢の息子さんである。他に候補地にしていたのは、松島と平泉だったが、結果的には山寺で正解だったかもしれない。
大晦日に雪が降り、安中榛名駅までは、息子の車に乗せてもらうことにした。土産は奮発しないといけない。旅先から携帯電話で注文をとって、帰りの運転も頼むことができた。路が凍結していて、女性の運転手というわけにはいかない。
山寺が正解だったというのは、雪と関係がある。水墨画のような山寺を見ることが出来たし、雪のためか初詣の客も意外と少なく、芭蕉が「山寺は、とりわけ清閑の地である」という雰囲気を味わうことができたからである。平泉の中尊寺あたりを訪ねていたら人出が多く、都会の雑踏の中にいる気分になったに違いない。今年のNHK大河ドラマは「義経」である。
『春の雲』、『夏の海』、『秋の風』、『冬の渚』と紀行文を書き、一区切りしたという気持は強い。失礼ながらに謹呈した友人知己諸氏にも、暫くは充電してからにしたいと申し上げたが、人生という旅は続いている。暮れになって、近年来の旅行症が生じてきて、紀行文を書き続ける気分になった。
深川の庵から、旅から戻って二年もしない年の暮れに、白河の関を越えたくなり、なにかに憑かれたかのようにじっとしていられなくなった芭蕉ほどではないにしても、この性癖は死ぬまで直りそうもない。
本を渡される方からしたらご迷惑に違いないから、紀行文は書き溜めて置いても、しばらくは発行しないでおこうとも考えている。芭蕉の『奥の細道』も旅が終って、五年後に出版されている。推敲に推敲を重ねて世に問う程の真剣さと器量はないから、そのような大それた野心があるわけではない。ただ、テーマと本の名前は決めておこうと思う。『翁への道』という書名にした。翁とは、もちろん芭蕉を指しているが、これから年を重ねていくであろう自分自身のことでもある。旅先は、芭蕉ゆかりの地であることも意識したいし、そうした旅を重ねながら芭蕉という人の人生観を少しでも理解したいという意味も含まれている。
芭蕉を慕い、その足跡を辿りつつ本を書いた作家や俳人は数多い。それほどに、日本人にとって芭蕉は魅力的な人物である。既に読んだ作品の中でも、俳人の加藤楸邨の『芭蕉の山河―おくのほそ道私記』(読売新聞社)、『月山』で芥川賞を晩年近くに受賞した作家、森敦の『われもまた おくのほそ道』(日本放送出版協会)は、自分の体重をかけて書いている雰囲気のある好著である。体重をかけていると言ったのは、読者の意識に迎合するような書き方ではないというほどの意味である。二人の著名な先人の足元には及びもしないが、『翁への道』も全体重をかけて書くようにしたい。そのためには、芭蕉の句にさらに多く触れてみなくてはならない。加えて自分の心の識を高めなければならないが、後者の方が数十倍大変なことである。
東北新幹線から山形新幹線となり、板谷峠に向う山間の風景は雪景色である。雪も降っている。昨年の元旦とは違う雪国山形となった。上杉鷹山の米沢、温泉地と歌人斎藤茂吉で知られる上山のあたりも一面の銀世界であった。山形駅の改札の出口には、同志社大学時代の友人が出迎えてくれていた。年賀状のやりとりは続けていたが、会うのは三十年ぶりである。出かける前に電話したのだが、奥さんが出て
「何しろ三十年ぶりなので顔がわかるでしょうか。ところで、髪の毛なんか薄くなったりしていて」
と失礼なことを聞いてしまった。五〇代になった友人の髪は健在であった。そのことを彼に話すと
「それは、あなたのことでしょうよ」
と逆襲されてしまった。
ただ会って、話をしてみるといっぺんに記憶が蘇って来るから不思議である。駅構内の店でコーヒーを飲みながら話すと、立て板に水のように話が途切れない。同行の友人に申し訳ないようである。仕事のこと、家族のこと。驚いたのは、会社では英語を日常話して仕事をしているのだという。会社が外資系で、社長もアメリカ人。従業員も外国人が多いからだという。
「文法などは、あまり気にしないでサ。ブロークンイングリッシュというやつかな。初めは、ヒアリングができなくて困ったけれど、離すのか持っているかのどちらかを指示されたとき、間違えば大変なことになる場面があったが、そういうときは、不思議と理解できるものだヨ」
標準語でしゃべっているが、山形弁の訛りである。でもこうした言い方も失礼ではある。大学時代の印象は、どこかナイーブな印象があった。今の彼の言動はエネルギッシュそのものである。ただ、親切な人ということでは、昔も今も変わっていない。
駅に近い山形市内で電気店を経営していたが、先年お父さんが他界し、十数年前からサラリーマン生活である。会社は米沢市にあるという。
「今、もう一度心理学の勉強をしたいと本当に思っている。少し時代が早すぎたのかな」
と、現在の仕事に大学時代に専攻した学問を生かせていないことが残念そうである。
山寺には、彼の自家用車で行くことになった。市内見学のガイドもしてくれた。有名な芋煮会の大鍋のある場所にも案内してくれた。蔵王から発する馬見ヶ崎川の河岸を通る国道の脇に置かれている。

山寺の正式な名称は、宝珠山立石寺といい、貞観二年(西暦八六〇年)に慈覚大師(円仁)によって開山された、比叡山延暦寺の別院である。根本中堂もある。山全体に堂や坊があって、奥の院まで行くには千余段の石段を登らなければならない。
慈覚大師は、伝教大師、最澄の弟子で、天台宗第三代座主である。俗名を円仁といった。遣唐使として中国大陸に渡り天台宗を学んだ。『入唐求法巡礼行記』は、自作の旅行記として評価が高い。下野(現在の栃木県)の生まれで、東北地方の寺院の建立に力を尽くした。平泉の中尊寺や毛越寺も慈覚大師ゆかりの寺である。大師という称号は、朝廷からのもので僧侶の中で歴史上何人もいない。
山寺芭蕉記念館は元旦で閉館になっていたが、「風雅の国」で軽い食事ができた。仙山線の山寺駅側にあって、高台であるため、山寺の全体を見ることができる。水墨画のような風景はこの場所から見ることができたのである。まさに山寺であった。
松尾芭蕉がこの地を訪れたのは、元禄二年の七月十三日の午後三時頃であった。尾花沢に泊まり、その地の人々に勧められて朝早く出かけることになったのである。予定のコースにはなかったのである。この勧めを断っていたら名句
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
は生れなかったわけである。
芭蕉は推敲の人と言って良いくらい、何度も何度も句を練り直している、蝉の句も例外ではない。最初は
山寺や 石にしみつく 蝉の声
それが
さびしさや 岩にしみ込 蝉のこゑ
となり、『奥の細道』の中に配置されたときには
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
となったのである。デッサンから完成した画に至るまでの画家の作業にも似ている。芭蕉は、自分の心にピタッとはまるまでは推敲を止めなかったのである。練りに練るということは辛い作業に違いない。しかし、完成した時の喜びは大きい。
寺の前の店に駐車して、参拝することにしたのは良いが、石段は雪で覆われ、しかも踏み固められている。気を許せば滑って転倒する。芭蕉がこの石段を登ったのは夏である。四〇代半ばの杖が手放せない当時では初老の芭蕉と比べても条件が遥かに悪い。同行してくれた友人は曽良ではないが、山登りの愛好家ということもあり
「せっかく山寺に来たのだから登りましょうよ」
と先頭をきって登り始めた。案内人の山形の友人は、電気店を営んでいた頃、電気器具を背負ってこの石段を何度も登ったことがあるらしい。それでも当時は若かったに違いないから苦にはならなかったであろう。蝉塚のある所までということで、ゆっくり登ったのだが、手摺につかまったらかえって滑りやすいことに気づいた。見かねた山形の友人は
「カメラを持ってあげるよ。それにしてもこれでは、岩にしみいるは、凍みいると変えなければならないね」
と上手いことを言う。
閑けさや 岩に凍み入 靴の音
酔狂で句は作って見たが川柳にもなっていない。
結局、蝉塚を通りすぎて、仁王門まで登ったが、帰りは手摺にしがみ付きながら、上りの倍近くの時間がかかってしまった。

車を駐車していた店で、そばを食べることにしたが、石段のぼりのおかげで実に美味かった。名物の「力こんにゃく」も醤油味がしみて格別な味がした。『翁への道』の起点になった山寺行きは、前途の険しさを思い知らされるものがある。ただ、友人との再会は心に残るものが多かった。息子さんの受験が済んだら、家族連れで群馬に来てもらい、ゆっくり温泉にでも浸かってもらいたいと心底思った。
山寺の紹介は芭蕉に任せたい。
「山形領に立石寺と云山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊清閑の地也。一見すべきよし、人々のすゝむるに依て、尾花沢よりとつて返し、其間七里ばかり也。日いまだ暮ず。梺の坊に宿かり置て、山上の堂にのぼる。岩に巌を重て山とし、松柏年旧、土石老て苔滑に、岩上の院々扉を閉て、物の音きこえず。岸をめぐり、岩を這て、仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行のみおぼゆ。
閑さや岩にしみ入蝉の声」
尾花沢から山寺まで二十八キロを歩き、その足で石段を登った芭蕉の健脚には脱帽する。「山上の堂」とは、どのあたりまでだったのであろうか。蝉の種類は、何であったかという後世の論争より、余程興味を抱いた。
Posted by okina-ogi at 07:27│Comments(0)
│旅行記