グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年06月27日
『藤村詩抄』島崎藤村著 岩波文庫 648円
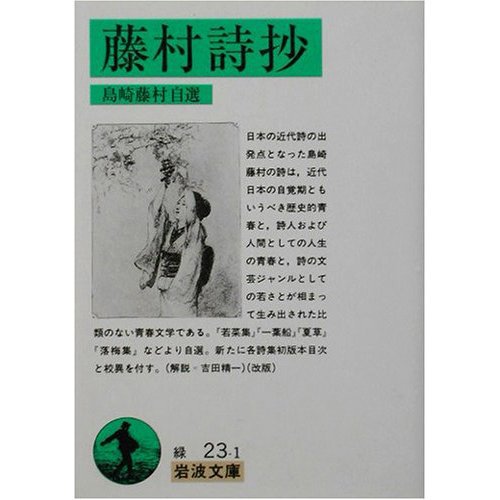
詩人、島崎藤村の世界にも触れておきたい。藤村の詩集は、青年期の短期間に泉のように湧き出たという感じがする。25歳の頃、日清戦争の直後の時代である。明治学院、東北学院を辞し、小諸へ教師として赴任する前である。父親の狂死、友人北村透谷の自殺、教え子との恋愛、そして病死。若くして、人生の無常観を意識したことは、容易に想像できる。芭蕉や西行に惹かれ、長い一人旅も経験している。千曲川旅情の歌に出てくる遊子(旅人)はまさに藤村自身である。
『若菜集』、『一葉舟』、『夏草』、『落梅集』の中から、藤村自身が詩を選び、昭和の初期に出版したのがこの詩集である。美しい言葉と哀調のメロディーに包まれた詩が多い。旧制高校の学生たちは、心躍るように藤村の詩を読んだのだろう。明治後期から大正生まれの人は少なくなっているが、青年期に出会った藤村の詩は、彼らをロマンチックな世界に誘ったであろう。
2014年06月24日
心に浮かぶ歌・句・そして詩162

登山
雪渓をこえて
高ねにのぼる
登るに従って眼界ひらく
気すみて心さわやかなり
珍しき花
絢爛のむしろをしく
雷鳥ひなを抱いて
しゃくなげの間にねむる
山頂はるかに望む
雪の連峰
―白馬岳にて―
後藤静香『権威』より
山登りは、趣味の一つだが、これほどの高山に登ることは数少なく、乗鞍岳に登ったのが最も高い標高の山ということになる。この詩にあるような風景、充分連想できる。富士山が日本の最高峰だが、多分一生登ることはないだろう。これほどの山は、遠くから眺める方が良いと思っている。
人生も山登りに例えてみるのも面白い。その中でいちばん辛いのは、心の高さ、深さを求めることである。仏教哲学に唯識というのがある。仏教では、九識が最も高い心の層だという。ここまでいくと、世界はどのように見えてくるのだろうか。「どの人を見ても、どの自然を見てもただ懐かしい」。こうなると、だいぶ九識に近い心に居ると言えるのではないだろうか。「見るもの、聞くもの全て懐かし」。
凡人は、楽な低地を歩き続けるので、視野は開けてこない。仲良しクラブにいて、それ以外の人や、異なる考えの人を避けるような生き方は、好ましくない。
2014年06月23日
マサキの挿し木

自宅は、所有する農地を転用して建てたので、敷地と農地が一体のようになって、道路との境に垣根も塀もない。もともと家を塀で囲むなどという考えはなかったので、庭が芝なので、垣根代わりにバラを植えておいた。バラは、管理が大変で蔓バラと真紅の薔薇が残っているだけになってしまった。補強することもあったが、数年すると枯れてしまって、本格的な垣根にすることにした。
実は、南面は、長野新幹線が掘割のようにして、近くを通っているので、防音のために塀がある。景観的にもよろしくないのでマサキの垣根になっている。20年以上になり手入れもそれほどしていないので、高さは揃えているが伸び放題という感じになっている。
マサキの挿し木は、それほど難しくないという友人のアドバイスがあったので、梅雨の時期を選んで挿し木に挑戦することにした。30本くらい無造作に畑の空いているところにさして見た。半日蔭位の場所が良いということだが、日当たりのよい場所なので人工的に日蔭を作ることにした。成功するかは数週間後にわかる。雨のない日は、水やりが欠かせない。
2014年06月21日
『風俗小説論』中村光夫著 講談社文芸文庫 1296円

書棚のどこかにこの本は埋もれていると思う。群馬県立土屋文明記念文学館で田山花袋の企画展を見に行き、自然主義文学の系譜に触れた。郷土の文豪には失礼とは思ったが、関心は、島崎藤村に向き、『春』、『桜の実の熟する時』、『千曲川のスケッチ』を読んだ。すっかり、小説の主人公、岸本捨吉(島崎藤村)の世界に没入してしまった。藤村の生涯も重なり、明治中期以降の時代世相の臭いを嗅ぐことができた。
『風俗小説論』は、大学時代に読んだのだと思うが、いやに記憶に残る本である。私小説という概念を知らされ、著者は痛烈な批判を加えていたように思う。そのやり玉にあがったのが『蒲団』である。どこか納得するところがあったので、田山花袋を敬遠することになったのだろう。高校時代に『田舎教師』を読んで暗い気持ちになったことも無関係ではない。還暦を過ぎた今日と青年時代の物の考えは変わっているかもしれない。もう一度書棚からこの本を取り出して読んでみようと思う。
2014年06月19日
介護保険制度の改定
6月19日の新聞各紙で、平成15年度からの介護保険の改正点を報道している。その内容は、それらを読んでいただきたい。改悪だという見解を持つ人もいるだろうが、所得による介護負担や、保険料を変更したことは理解できる。年金生活者である、低所得高齢者の保険料を引き下げたのは、給付の増加によって保険料負担が増える流れからすれば、必要な措置である。また、介護負担を所得上位の人に2割負担を求めるのも妥当だと思う、2割負担になる人は年金で280万円以上だから、それほど多くの人ではない。月額25万円の年金を受給できる人は50万~60万人だという数字が示されている。
高収入があって年金が多く貰える層は、医療でも介護でも負担が多くなっても、社会保険の恩恵を受けられるのだから、負担してもらいたい。それよりも、国全体の介護保険制度の財源が問題になる。健康な老後を過ごすことと、経済の安定成長が求められる。
高収入があって年金が多く貰える層は、医療でも介護でも負担が多くなっても、社会保険の恩恵を受けられるのだから、負担してもらいたい。それよりも、国全体の介護保険制度の財源が問題になる。健康な老後を過ごすことと、経済の安定成長が求められる。
2014年06月18日
『千曲川のスケッチ』島崎藤村著 新潮文庫 391円

島崎藤村は、明治32年から小諸義塾の教師として7年間長野県小諸に住んだ。懐古園には、千曲川旅情の歌碑文が残っている。懐古園からも千曲川の流れが見える。島崎藤村は明治学院、東北学院の教師を経て、詩人として世に出たが、後に小説に転じた。その中間点でもあるこの時期に、写生文としての『千曲川のスケッチ』を書いた。明治時代の農村風景が描かれており、時代考証の資料にもなる。
大作『破戒』の素材になっている文章も綴られている。歌人や俳人が自然をスケッチするように、散文での自然描写も見事である。上田、小諸、佐久、あたりの千曲川流域の知名度を上げた島崎藤村のこの作品は、一度は通読しておきたい。
2014年06月17日
社会福祉法人の内部留保
数日前の日本経済新聞を見ていたら、社会福祉法人が資金を多く内部に持っている実態に対し、本来の公益法人としてふさわしい活動に、その資金を活用する方向に議論が進められているという内容で、実行できない法人には行政指導も必要というものだったように記憶している。
最近できた社会福祉法人のことは良く分からないが、特別養護老人ホームは、介護保険制度に移行する前は、公費で運営されていた。措置費という名称で、そのお金の使い方は、行政指導により細かに使途が決められていた。入居者のために使われる事業費と、職員の人件費に使われる事務費は、区分され流用は認められなかった。事業費が余ったからといって人出を増やして介護サービスを充実させようとすることもできなかった。かなり硬直した運営になっていたような気がする。
その結果、資金が法人内部に蓄積したということも言えるが、ある程度の資金を内部留保しておくことは、公益法人としての社会福祉法人としては、長く安定して運営されるためには、必要なこととも言える。安倍政権になって、経済の活性化が目標にされているが、個人が預金を投資にまわすことを促すのとはわけが違う。この内部留保した資金を株式に運用するなどとは言っていないが、社会福祉法人は、原則元本割れのリスクのあるものに運用してはいけないことになっている。
今でも、社会福祉法人には助成金や補助金による経営支援や税の免除などの特権が残っているが、民間からの尊い浄財の支援もある。土地の取得や建築費には多額の自己資金が必要だし、設備の維持管理も大変である。内部留保を必要以上にすることは意味がないが、計画的に引当金として計上し、安定的に運営することが肝要だと思う。
「無駄遣いはせず、公平にしかも効率的に公金は使うのが大事」と元厚生省(当時)の老人福祉専門官を歴任した数年前に故人になった森幹郎氏のいう通りであって、今もこの言葉は、内部留保されたお金の使い方として参考にしたい。
最近できた社会福祉法人のことは良く分からないが、特別養護老人ホームは、介護保険制度に移行する前は、公費で運営されていた。措置費という名称で、そのお金の使い方は、行政指導により細かに使途が決められていた。入居者のために使われる事業費と、職員の人件費に使われる事務費は、区分され流用は認められなかった。事業費が余ったからといって人出を増やして介護サービスを充実させようとすることもできなかった。かなり硬直した運営になっていたような気がする。
その結果、資金が法人内部に蓄積したということも言えるが、ある程度の資金を内部留保しておくことは、公益法人としての社会福祉法人としては、長く安定して運営されるためには、必要なこととも言える。安倍政権になって、経済の活性化が目標にされているが、個人が預金を投資にまわすことを促すのとはわけが違う。この内部留保した資金を株式に運用するなどとは言っていないが、社会福祉法人は、原則元本割れのリスクのあるものに運用してはいけないことになっている。
今でも、社会福祉法人には助成金や補助金による経営支援や税の免除などの特権が残っているが、民間からの尊い浄財の支援もある。土地の取得や建築費には多額の自己資金が必要だし、設備の維持管理も大変である。内部留保を必要以上にすることは意味がないが、計画的に引当金として計上し、安定的に運営することが肝要だと思う。
「無駄遣いはせず、公平にしかも効率的に公金は使うのが大事」と元厚生省(当時)の老人福祉専門官を歴任した数年前に故人になった森幹郎氏のいう通りであって、今もこの言葉は、内部留保されたお金の使い方として参考にしたい。
2014年06月13日
心に浮かぶ歌・句・そして詩161
見えねど美し
朝ぎりのなかに
馬子うたきこゆ
むすめ見えねど美し
紺がすり 赤だすき
白い菅がさ 稲田にそろう
顔は見えねど美し
銀河のほとり相思の人
七夕さまは
見えねど美し
後藤静香『権威』より
馬に乗って花嫁が嫁ぐ風景、大ぜいして田植をする風景は、すっかり見られなくなったが、日本の田舎の懐かしい風景である。「銀河のほとり相思の人」とは彦星と織姫のこと。「見えねど美し」、良い言葉である。金子みすずの詩が思い浮かぶ。
青いお空のそこふかく
海の小石のそのように
夜がくるまでしずんでる
昼のお星はめにみえぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
ちってすがれたたんぽぽの
かわらのすきにだァまって
春のくるまでかくれてる
つよいその根はめにみえぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
「星とたんぽぽ」という詩である。「見えぬけれどもあるんだよ」もまた良い感性。
朝ぎりのなかに
馬子うたきこゆ
むすめ見えねど美し
紺がすり 赤だすき
白い菅がさ 稲田にそろう
顔は見えねど美し
銀河のほとり相思の人
七夕さまは
見えねど美し
後藤静香『権威』より
馬に乗って花嫁が嫁ぐ風景、大ぜいして田植をする風景は、すっかり見られなくなったが、日本の田舎の懐かしい風景である。「銀河のほとり相思の人」とは彦星と織姫のこと。「見えねど美し」、良い言葉である。金子みすずの詩が思い浮かぶ。
青いお空のそこふかく
海の小石のそのように
夜がくるまでしずんでる
昼のお星はめにみえぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
ちってすがれたたんぽぽの
かわらのすきにだァまって
春のくるまでかくれてる
つよいその根はめにみえぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
「星とたんぽぽ」という詩である。「見えぬけれどもあるんだよ」もまた良い感性。
2014年06月11日
梅の市況

梅の相場がおもわしくない。価格は、需要と供給で決まるが、需要が減っているのか、それとも豊作で供給が増えているのか、その理由はわからない。
東京青果市場で調べると、群馬産のウメは、キロ350円位。梅酒用の白加賀種で粒の大きい3Lサイズで高値のはずだがこの値段。Lや2Lサイズは記載されていないのでわからないが、200円台かも知れない。
ウメの市況蘭は、果実の所に載っているのかと思ったら、野菜の蘭にある。果実と思いこんでいたのは、兼業農家として恥ずかしい限りである。
こんな低価格が続くと、梅農家も減るに違いない。農地転用をして太陽光発電に切り替えている農家もある。高齢化と、後継者不足ということだけでも梅農家は、減少している。
2014年06月05日
梅の出荷

梅の産地と言えば、和歌山県である。全国ダントツの生産量を誇っている。南高梅という品種は、漬け梅に適していて、高価で売られている。南高(なんこう)という名前の由来は知らないが、楠公を彷彿させる響きがある。千早城は、和歌山県境に近い。
群馬県も梅の産地で、関東甲信越では、生産量は多い。ただし、和歌山県の十分の一に過ぎない。和歌山県の出荷が早いから、近年値崩れすることが多く価格競争で苦戦を強いられている。こちらは、白加賀という品種が多く、梅酒に適している。一時健康ブームに乗り、青いダイヤと言われた時期もあった。一キロ700円で市場で取引されたのは、遠い過去になってしまった。
今、梅の出荷の最盛期になっている。空が明るくなり始まる5時頃から、手でもいで、選果して出荷する。消費者の嗜好で、キズものは選外になる。ジュースなど加工用になるが、価格は格段と低くなる。成分は同じ事を考えるともったいない話である。
2014年06月04日
『春』島崎藤村著 新潮文庫 590円(税別)

久しぶりに、島崎藤村の小説を手にした。タイトルがすっきりしているが、内容は青年時代の島崎藤村の苦悩が書かれている。古典と言われるような小説を読むのは、何十年ぶりという感じで、数学や俳句から遠ざかった人間のように、その世界にしたる感覚がなかなか戻ってこないのには、閉口した。
島崎藤村には、関心があるがその生涯と文学作品には、あまり触れていない。『破戒』と『夜明け前』は、読んでいる。文学に関心が強かった高校時代の頃だから、読後感はとうに消え去り、あらすじなどは覚えていない。
たまたま、群馬県立土屋文明記念館で田山花袋の企画展が開催されており、図書のコーナーにこの本があったので、手にしたということに過ぎない。同じ自然主義文学者でも、田山花袋の『蒲団』は読む気がしなかったのでこの本に手が伸びたのかもしれない。
今年の元旦、大磯に行き、島崎藤村が晩年過ごした家の前を通ったことも、まんざら無関係ではなさそうである。あまり深入りはしなくても、もう一冊くらい彼の小説を読んでも良いと思うようになった。『桜の実の熟する時』という作品である。
小説『春』に登場する人物は、明治女学院で教師をしていた頃の友人達で、とりわけ北村透谷と教え子の佐藤輔子の存在が大きい。透谷は、自殺。輔子は病死。二人の大きな存在を失った藤村の苦悶が描かれており、文学者として生きていく決意も感じられる小説になっている。もちろん、登場人物は実名で出てくるわけではない。
2014年06月03日
『富岡製糸場と絹産業遺産群』今井幹夫編著 ベスト新書 933円+税

富岡製糸場と絹産業遺産群が、6月に世界遺産に登録されることが確実になった。名乗りを上げた時、その確率は少ないと思っていたが、この本を読んでみると、そうとも言えなかったと感じた。創業当時の建物が、良く保存されていることと、100年以上にわたって製糸場として機能していた事実は、驚きに値する。工場などは、立て替えられて機能的な面が優先され建て替えられるのが普通である。
官営の時代は以外と短かかったが、民営になって良く維持された。片倉工業は、最後の会社になったが、操業を停止してからも、この歴史的、文化価値のある建物を良く保存した。諏訪湖にいまも片倉館というレトロな建物が残り、温泉施設として使われているが、この会社の社風とも無関係ではないようだ。
しばらくは、富岡製糸場見学が続くだろうから、遠方の来客案内の良い手引きにもなるだろう。

