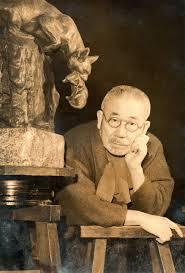2013年09月17日
『翁草』(拙著)ザビエルの来た町
ザビエルの来た町

一五四九年、イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが日本へキリスト教を布教するために薩摩(鹿児島県)に上陸した。アンジロウ(ヤジロウ)という日本人が同行していた。彼は既に洗礼を受けていた。薩摩は、彼の生まれ故郷であった。
薩摩の領主は、島津貴久であった。ザビエルに布教を許す。後に秀吉や、徳川幕府がキリスト教を過酷なほどに弾圧するが、はるかヨーロッパから来た異国の人への興味が、警戒心すら起こさせなかったのかもしれない。当然、ザビエルに付き添った、アンジロウが通訳したであろうし、人格的にもすぐれた人物であったと想像される。
ザビエルは、室町幕府のある京都で布教する構想を持った。多くの信者を獲得するには、政治、文化の中心地が良いと考えたのは、大胆とも見えるが、結果的にも、彼の布教の時間は限られていたのである。しかし、都での布教をあきらめざるを得なかった。応仁の乱で都は荒廃していたし、比叡山の僧と論戦の機会も持てなかった。天皇への謁見の許可も出なかった。
鹿児島から都への往路、平戸や博多、下関、山口に立ち寄っているが、復路、布教の拠点としたのが、中国地方の有力守護大名であった大内義隆のいた山口であった。大内義隆は、武人というよりは文化人で、朝鮮や、明との貿易で得た富は軍事に充てなかった。中国地方には、尼子氏や、勢力は小さかったが広島の毛利氏との軍事的緊張のあった時代、結果は家臣である陶氏の謀反により自刃するという結果になる。

ザビエルが義隆に謁見した当時の山口は、京都の文化の影響が色濃く、西の京都といわれるのにふさわしい町並みであったという。今日でもその面影を残しているが、瑠璃光寺の五重の塔は、その代表的な建造物である。一四四二年に竣工しているので、ザビエルも百年余りを経た重厚なこの塔を見たのであろうが、書簡に記述はない。
国宝「四季山水図」、「秋冬山水図」、「天の橋立図」の水墨画で知られる雪舟も時代は少し遡るが大内氏の庇護を受け、山口に長く滞在したことで知られている。この塔は、雪舟が山口を訪れた時にも建てられていたことも重ね合わせてみると不思議な感慨が生まれる。薬師寺の東塔、興福寺の塔、京都の東寺の塔といった古都にある塔に決して見劣りはしない。もちろん国宝である。
山口の滞在期間は、半年ほどであったが、布教の手ごたえを感じ、信者も得ている。ザビエルの日本滞在は、二年余りであるが、大分では、若き大友宗麟に会い、晩年には宗麟はクリスチャン大名になる。天正遣欧少年使節として知られる、伊藤マンショ、中浦ジュリアンらのローマ法王庁へ送る行動へと繋げたのは、間接的ではあるが、ザビエルの功績である。大分を最後の布教の地としてザビエルは日本を去るのだが、一年後の一五五二年には、中国の布教を夢見ながら帰天する。四十六歳の人生であった。
二〇〇五年の十一月、「ザビエルの来た町」山口市を訪ねることにした。今回は、観光旅行というよりは、山口市の市民会館で開催された、ホスピスの全国的研究会「日本死の臨床研究会」に出席するのが目的であった。末期癌患者の医療や看護、家族の心のケアへの取り組みは、日本では歴史は古くはないが、この会は、今年で二九回を数える。
十五年近く前に、緩和病棟として癌の末期患者への医療が制度化され、現在一五〇ほどの施設ができているが、地域ケアとして行う試みも生まれている。ホスピスケアの日本で先駆けとなったのは、浜松聖隷事業団や大阪の淀川キリスト教病院で、原義雄、柏木哲夫といった医師の働きが知られている。柏木哲夫は、現在でもこの研究会の世話人代表で、九〇歳を超える年齢で医師として現役であり、文化勲章を受章した日野原重明は顧問になっている。
ホスピスケアでは死の問題を避けて通ることはできない。宗教と密接な関係もある。キリスト教界がリーダーシップをとっているようにも見えるが、仏教界や独立行政法人や公立の医療機関の取り組みもある。日々、癌の末期患者の生を見つめ、心や生理的痛みに向き合うスタッフのことを考えると、部外者からみると敬意を表するしかないのだが、参加者の熱意にはさらに頭が下がる。全体でのシンポジウムでの発表もあるが、小さな研究発表の場も設けられている。全て実践報告となっている。「死の臨床研究会」の会の名前が相応しい。
特別講演があり、昨年開催された茨城県つくば市では、『大往生』の著者、放送作家、作詞家の永六輔、解剖学者、養老孟司、「生きがい論」や「前世療法」の飯田史彦が講師となった。今年は、金子みすゞ記念館の館長で詩人の矢崎節夫の特別講演があった。タイトルは、「―日本人の精神性―金子みすずの世界といのち」であったが、無名詩人に近い金子みすゞを世に出した人の迫力には圧倒された。矢崎の父親も癌で亡くなっている。夫人も五年前に癌治療を受けている。体験の話も貴重だが、みすゞの詩の捉え方が一貫している。矢崎が強調したことを短く言えば「いのちへの優しさ」ということになるのだろう。「みすゞコスモス」という言葉を使い、地球が生んだ四十億年のいのちにも話が及ぶ。
矢崎節夫が早稲田の学生時代に強烈に心を揺り動かされた金子みすゞの詩は
大漁
朝焼け小焼だ
大漁だ
大羽鰮
大漁だ。
浜は祭りの
やうだけど
海のなかでは
何万の
鰮のとむらひ
するだろう
であるが、この詩には喜びと悲しみを対にした意識があるというのである。辛さと幸せ、光と影、それは表裏一体である。仏教に不一不二という言葉があるがそれに似ている。
「患者さんが痛いねと言ったら、痛いねと応えられる人であってほしい」というのが参加者へのメッセージの一つであった。表現を変えて、「私とあなた」という関係ではなく、「あなたと私」の関係で考えるようにしてほしい。相手の立場に立って考えるという月並みな表現でわかるようなものではなく、「こだま」がなくてはならないともいう。「答える」は「応える」というという文字を使うのがふさわしい。詩人らしい表現とも感じたが、矢崎の宗教観には背景に仏教がある。金子みすゞの郷土、山口県仙崎は仏教への信心の深い土地である。
冒頭に、ザビエルの日本での伝道のあらましを書いたが、矢崎節夫は、まるで金子みすゞ教の伝道者のようにも見えた。決してこの事は、矢崎の講演を揶揄しているのではない。実際、金子みすずの詩は、教科書にも載り、多くの人々の心を捉えている。忘れかけていた、日本人の優しさを、金子みすゞが気づかせ、矢崎が解説して見せている。
布教について考えてみる。ザビエルが日本に来て説教したのは、キリストの十字架上の悲劇的な結末である。パウロのように復活の話はほとんど語らなかったという。無力な人に同情する感性は、古くから日本人の中にあったのである。加えて、十字架に架けられて、死に至る苦しみの中で、恨み言を言わなかったことも驚異に思ったであろう。
「主よ、主よ、なぜ我を見棄て給うか」はキリストの絶望の言葉でなく、「我は汝のみ名を告げ、人々のなかで汝をほめたたえん」と神を讃美し、「主よ、わが魂をみ手に委ねたてまつる」と言って息を引きとったのである。

ペトロというキリストの弟子は、人間誰もが持つ死への恐れの強かった人物であったと思われる。ユダのようにキリストを裏切るようなことはしなかったが、たびたび保身をはかり、キリストを知らないといって身を隠している。ユダヤ教の戒律や神殿への礼拝も守ったし、異邦人への布教にも積極的ではなかった保守的とも言われてもしかたない行動もしている。ローマ市民権を持ち、イスラエルの国の外に暮らしていたユダヤ人のステファノが殉教するのも遠くから見ていたし、パウロの布教も過激に思い、協力的ではなかった。相当の政治家的キリスト教徒と言えるが、最後は、ローマで逆さ十字架に架けられて殉教したと伝えられている。彼の墓の上にバチカンの聖堂が立てられ、ローマ法王庁の始祖のようになっていることを考えると、キリストを想い続けた偉大な人物なのかもしれない。しかしながら、ペトロよりも、はるばる日本まで伝道に来たザビエルの熱情、権力者であったローマ帝国中枢部への伝道といったパウロの不屈の精神に惹かれるのである。
棄教について考えてみる。遠藤周作の小説に『沈黙』がある。吊るし刑に苦しむ信徒の声に棄教を迫られる神父の場面は、自分がその立場になったらどう行動するだろうかという問いを突きつけられる。結果は、「転ぶ」のであるが、神父には、キリストの

「自分はお前たちに踏まれるため、この世に生まれてきたのだから踏絵を踏んでかまわない」
という声を聞くような気がするのである。神父が棄教することによって、信徒の命が助けられるのであれば、棄教も愛の行為とも言えなくはない。他者が助かるのであれば、自分の信念や思想を捨てても許されるのではないだろうか。「転向」、「棄教」を咎められるほど人は強くない。ペトロの繰り返す保身は、信仰の中断でもなかったし、棄教でもなく最後は殉教の道に至ったことを考えると人としては、立派過ぎると言えるかもしれない。
ホスピスの研究会に刺激され、ザビエルに想いを馳せ、とりとめもなく宗教について書きなぐってしまった。他人の痛みをどうしたらわかるのか、ということは別にホスピスケアに携わる人だけの問題ではない。「こだま」という良い言葉を矢崎氏に教えてもらった。キリストの愛、金子みすずの詩は他者に響くのである。
山口市は、県都でありながら温泉街が市内にある珍しい町である。湯田温泉は、全国に知られている。山陽新幹線の開通後、小郡に新山口駅ができ、山口市へのアクセスは良くなった。また、山口線は新山口駅から津和野までSLが走り、観光アピールになっている。宿にしたのは湯田温泉ではなく、防府市のビジネスホテルである。山口駅からは新山口駅で乗り換え、一時間以上かかる。夜八時過ぎに駅に着いたが、駅前はきれいに整備されていて、山口駅より開発が進んでいる。

翌日は、ゆっくり市内観光をする。観光名所として防府天満宮が有名であるが、雪舟の国宝「四季山水図」を所蔵する毛利博物館のある毛利家庭園は一見の余地がある見事なものである。山が背後にあって、庭園らしく見えたが、ゴルフ場というのには驚いた。借景として調和しているようには見えない。
毛利家庭園から徒歩で山裾を歩くと、国分寺や天満宮にたどり着くことができるが、途中の雰囲気は奈良郊外を歩いているような気分になる。山口県は、長門の国と周防の国からできていて、幕末の長州藩を防長二州と呼んだ所以はここにある。周防の国の中心が防府であり、ほうふと読む。
防府天満宮のお参り後、階段下の店が俳人種田山頭火のグッズを売っていった。店内に入ると焼き物、葉書、お菓子の土産物が並び、記念館のように写真や資料も展示されている。ご主人は種田山頭火の愛好会の役員もしているという。

防府は、山頭火の生まれた場所であることは意外と知られていないかもしれない。芭蕉のように旅の俳人としてのイメージが強いからである。それもどちらかと言えば、放浪のような印象がある。
歩かない日はさみしい
飲まない日はさみしい
つくらない日はさみしい
孤独と酒のなかに句を紡いだ人が山頭火であるが、店主の話と小冊子に書かれた彼の年譜を見て、納得できるものがあった。大地主から事業の失敗による破産。幼いときの母親の自殺。男の子をひとり残しての離婚。定職も長くもてない。人生の失敗者といわれても仕方がない。それでも俳句は書き続けた。俳句をつくらない日はさみしかったのである。俳句といってもいわゆる五七五の定形でなく自由律というもので、荻原井泉水や河東碧梧桐などが普及させようとした。
大正十五年から亡くなる昭和十五年までは、庵を結んだこともあったが、歩いて旅をし、俳句を作り続け、その作は一万首を超える。有名なのは
分け入っても分け入っても青い山
で、宮崎県の高千穂に近い場所で生まれている。ふるさとの句も多いが屈折した心境のものが多い
ふるさとは遠くして木の芽
雨ふるふるさとははだしであるく
うまれた家はあとかたもないほうたる
旅先で
日ざかりのお地蔵さまの顔がにこにこ
てふてふひらひらいらかをこえた
あどけない感じだが、芭蕉の野ざらし紀行のように旅に死す決意を感じさせる
おちついて死ねそうな草萌ゆる
母の死は、かれの人生を大きく支配したであろう。
母ようどんそなえてわたしもいただきます
山頭火の句も他者に響くが、彼に他者の愛は響いていたのであろうか。

一五四九年、イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが日本へキリスト教を布教するために薩摩(鹿児島県)に上陸した。アンジロウ(ヤジロウ)という日本人が同行していた。彼は既に洗礼を受けていた。薩摩は、彼の生まれ故郷であった。
薩摩の領主は、島津貴久であった。ザビエルに布教を許す。後に秀吉や、徳川幕府がキリスト教を過酷なほどに弾圧するが、はるかヨーロッパから来た異国の人への興味が、警戒心すら起こさせなかったのかもしれない。当然、ザビエルに付き添った、アンジロウが通訳したであろうし、人格的にもすぐれた人物であったと想像される。
ザビエルは、室町幕府のある京都で布教する構想を持った。多くの信者を獲得するには、政治、文化の中心地が良いと考えたのは、大胆とも見えるが、結果的にも、彼の布教の時間は限られていたのである。しかし、都での布教をあきらめざるを得なかった。応仁の乱で都は荒廃していたし、比叡山の僧と論戦の機会も持てなかった。天皇への謁見の許可も出なかった。
鹿児島から都への往路、平戸や博多、下関、山口に立ち寄っているが、復路、布教の拠点としたのが、中国地方の有力守護大名であった大内義隆のいた山口であった。大内義隆は、武人というよりは文化人で、朝鮮や、明との貿易で得た富は軍事に充てなかった。中国地方には、尼子氏や、勢力は小さかったが広島の毛利氏との軍事的緊張のあった時代、結果は家臣である陶氏の謀反により自刃するという結果になる。

ザビエルが義隆に謁見した当時の山口は、京都の文化の影響が色濃く、西の京都といわれるのにふさわしい町並みであったという。今日でもその面影を残しているが、瑠璃光寺の五重の塔は、その代表的な建造物である。一四四二年に竣工しているので、ザビエルも百年余りを経た重厚なこの塔を見たのであろうが、書簡に記述はない。
国宝「四季山水図」、「秋冬山水図」、「天の橋立図」の水墨画で知られる雪舟も時代は少し遡るが大内氏の庇護を受け、山口に長く滞在したことで知られている。この塔は、雪舟が山口を訪れた時にも建てられていたことも重ね合わせてみると不思議な感慨が生まれる。薬師寺の東塔、興福寺の塔、京都の東寺の塔といった古都にある塔に決して見劣りはしない。もちろん国宝である。
山口の滞在期間は、半年ほどであったが、布教の手ごたえを感じ、信者も得ている。ザビエルの日本滞在は、二年余りであるが、大分では、若き大友宗麟に会い、晩年には宗麟はクリスチャン大名になる。天正遣欧少年使節として知られる、伊藤マンショ、中浦ジュリアンらのローマ法王庁へ送る行動へと繋げたのは、間接的ではあるが、ザビエルの功績である。大分を最後の布教の地としてザビエルは日本を去るのだが、一年後の一五五二年には、中国の布教を夢見ながら帰天する。四十六歳の人生であった。
二〇〇五年の十一月、「ザビエルの来た町」山口市を訪ねることにした。今回は、観光旅行というよりは、山口市の市民会館で開催された、ホスピスの全国的研究会「日本死の臨床研究会」に出席するのが目的であった。末期癌患者の医療や看護、家族の心のケアへの取り組みは、日本では歴史は古くはないが、この会は、今年で二九回を数える。
十五年近く前に、緩和病棟として癌の末期患者への医療が制度化され、現在一五〇ほどの施設ができているが、地域ケアとして行う試みも生まれている。ホスピスケアの日本で先駆けとなったのは、浜松聖隷事業団や大阪の淀川キリスト教病院で、原義雄、柏木哲夫といった医師の働きが知られている。柏木哲夫は、現在でもこの研究会の世話人代表で、九〇歳を超える年齢で医師として現役であり、文化勲章を受章した日野原重明は顧問になっている。
ホスピスケアでは死の問題を避けて通ることはできない。宗教と密接な関係もある。キリスト教界がリーダーシップをとっているようにも見えるが、仏教界や独立行政法人や公立の医療機関の取り組みもある。日々、癌の末期患者の生を見つめ、心や生理的痛みに向き合うスタッフのことを考えると、部外者からみると敬意を表するしかないのだが、参加者の熱意にはさらに頭が下がる。全体でのシンポジウムでの発表もあるが、小さな研究発表の場も設けられている。全て実践報告となっている。「死の臨床研究会」の会の名前が相応しい。
特別講演があり、昨年開催された茨城県つくば市では、『大往生』の著者、放送作家、作詞家の永六輔、解剖学者、養老孟司、「生きがい論」や「前世療法」の飯田史彦が講師となった。今年は、金子みすゞ記念館の館長で詩人の矢崎節夫の特別講演があった。タイトルは、「―日本人の精神性―金子みすずの世界といのち」であったが、無名詩人に近い金子みすゞを世に出した人の迫力には圧倒された。矢崎の父親も癌で亡くなっている。夫人も五年前に癌治療を受けている。体験の話も貴重だが、みすゞの詩の捉え方が一貫している。矢崎が強調したことを短く言えば「いのちへの優しさ」ということになるのだろう。「みすゞコスモス」という言葉を使い、地球が生んだ四十億年のいのちにも話が及ぶ。
矢崎節夫が早稲田の学生時代に強烈に心を揺り動かされた金子みすゞの詩は
大漁
朝焼け小焼だ
大漁だ
大羽鰮
大漁だ。
浜は祭りの
やうだけど
海のなかでは
何万の
鰮のとむらひ
するだろう
であるが、この詩には喜びと悲しみを対にした意識があるというのである。辛さと幸せ、光と影、それは表裏一体である。仏教に不一不二という言葉があるがそれに似ている。
「患者さんが痛いねと言ったら、痛いねと応えられる人であってほしい」というのが参加者へのメッセージの一つであった。表現を変えて、「私とあなた」という関係ではなく、「あなたと私」の関係で考えるようにしてほしい。相手の立場に立って考えるという月並みな表現でわかるようなものではなく、「こだま」がなくてはならないともいう。「答える」は「応える」というという文字を使うのがふさわしい。詩人らしい表現とも感じたが、矢崎の宗教観には背景に仏教がある。金子みすゞの郷土、山口県仙崎は仏教への信心の深い土地である。
冒頭に、ザビエルの日本での伝道のあらましを書いたが、矢崎節夫は、まるで金子みすゞ教の伝道者のようにも見えた。決してこの事は、矢崎の講演を揶揄しているのではない。実際、金子みすずの詩は、教科書にも載り、多くの人々の心を捉えている。忘れかけていた、日本人の優しさを、金子みすゞが気づかせ、矢崎が解説して見せている。
布教について考えてみる。ザビエルが日本に来て説教したのは、キリストの十字架上の悲劇的な結末である。パウロのように復活の話はほとんど語らなかったという。無力な人に同情する感性は、古くから日本人の中にあったのである。加えて、十字架に架けられて、死に至る苦しみの中で、恨み言を言わなかったことも驚異に思ったであろう。
「主よ、主よ、なぜ我を見棄て給うか」はキリストの絶望の言葉でなく、「我は汝のみ名を告げ、人々のなかで汝をほめたたえん」と神を讃美し、「主よ、わが魂をみ手に委ねたてまつる」と言って息を引きとったのである。

ペトロというキリストの弟子は、人間誰もが持つ死への恐れの強かった人物であったと思われる。ユダのようにキリストを裏切るようなことはしなかったが、たびたび保身をはかり、キリストを知らないといって身を隠している。ユダヤ教の戒律や神殿への礼拝も守ったし、異邦人への布教にも積極的ではなかった保守的とも言われてもしかたない行動もしている。ローマ市民権を持ち、イスラエルの国の外に暮らしていたユダヤ人のステファノが殉教するのも遠くから見ていたし、パウロの布教も過激に思い、協力的ではなかった。相当の政治家的キリスト教徒と言えるが、最後は、ローマで逆さ十字架に架けられて殉教したと伝えられている。彼の墓の上にバチカンの聖堂が立てられ、ローマ法王庁の始祖のようになっていることを考えると、キリストを想い続けた偉大な人物なのかもしれない。しかしながら、ペトロよりも、はるばる日本まで伝道に来たザビエルの熱情、権力者であったローマ帝国中枢部への伝道といったパウロの不屈の精神に惹かれるのである。
棄教について考えてみる。遠藤周作の小説に『沈黙』がある。吊るし刑に苦しむ信徒の声に棄教を迫られる神父の場面は、自分がその立場になったらどう行動するだろうかという問いを突きつけられる。結果は、「転ぶ」のであるが、神父には、キリストの

「自分はお前たちに踏まれるため、この世に生まれてきたのだから踏絵を踏んでかまわない」
という声を聞くような気がするのである。神父が棄教することによって、信徒の命が助けられるのであれば、棄教も愛の行為とも言えなくはない。他者が助かるのであれば、自分の信念や思想を捨てても許されるのではないだろうか。「転向」、「棄教」を咎められるほど人は強くない。ペトロの繰り返す保身は、信仰の中断でもなかったし、棄教でもなく最後は殉教の道に至ったことを考えると人としては、立派過ぎると言えるかもしれない。
ホスピスの研究会に刺激され、ザビエルに想いを馳せ、とりとめもなく宗教について書きなぐってしまった。他人の痛みをどうしたらわかるのか、ということは別にホスピスケアに携わる人だけの問題ではない。「こだま」という良い言葉を矢崎氏に教えてもらった。キリストの愛、金子みすずの詩は他者に響くのである。
山口市は、県都でありながら温泉街が市内にある珍しい町である。湯田温泉は、全国に知られている。山陽新幹線の開通後、小郡に新山口駅ができ、山口市へのアクセスは良くなった。また、山口線は新山口駅から津和野までSLが走り、観光アピールになっている。宿にしたのは湯田温泉ではなく、防府市のビジネスホテルである。山口駅からは新山口駅で乗り換え、一時間以上かかる。夜八時過ぎに駅に着いたが、駅前はきれいに整備されていて、山口駅より開発が進んでいる。

翌日は、ゆっくり市内観光をする。観光名所として防府天満宮が有名であるが、雪舟の国宝「四季山水図」を所蔵する毛利博物館のある毛利家庭園は一見の余地がある見事なものである。山が背後にあって、庭園らしく見えたが、ゴルフ場というのには驚いた。借景として調和しているようには見えない。
毛利家庭園から徒歩で山裾を歩くと、国分寺や天満宮にたどり着くことができるが、途中の雰囲気は奈良郊外を歩いているような気分になる。山口県は、長門の国と周防の国からできていて、幕末の長州藩を防長二州と呼んだ所以はここにある。周防の国の中心が防府であり、ほうふと読む。
防府天満宮のお参り後、階段下の店が俳人種田山頭火のグッズを売っていった。店内に入ると焼き物、葉書、お菓子の土産物が並び、記念館のように写真や資料も展示されている。ご主人は種田山頭火の愛好会の役員もしているという。

防府は、山頭火の生まれた場所であることは意外と知られていないかもしれない。芭蕉のように旅の俳人としてのイメージが強いからである。それもどちらかと言えば、放浪のような印象がある。
歩かない日はさみしい
飲まない日はさみしい
つくらない日はさみしい
孤独と酒のなかに句を紡いだ人が山頭火であるが、店主の話と小冊子に書かれた彼の年譜を見て、納得できるものがあった。大地主から事業の失敗による破産。幼いときの母親の自殺。男の子をひとり残しての離婚。定職も長くもてない。人生の失敗者といわれても仕方がない。それでも俳句は書き続けた。俳句をつくらない日はさみしかったのである。俳句といってもいわゆる五七五の定形でなく自由律というもので、荻原井泉水や河東碧梧桐などが普及させようとした。
大正十五年から亡くなる昭和十五年までは、庵を結んだこともあったが、歩いて旅をし、俳句を作り続け、その作は一万首を超える。有名なのは
分け入っても分け入っても青い山
で、宮崎県の高千穂に近い場所で生まれている。ふるさとの句も多いが屈折した心境のものが多い
ふるさとは遠くして木の芽
雨ふるふるさとははだしであるく
うまれた家はあとかたもないほうたる
旅先で
日ざかりのお地蔵さまの顔がにこにこ
てふてふひらひらいらかをこえた
あどけない感じだが、芭蕉の野ざらし紀行のように旅に死す決意を感じさせる
おちついて死ねそうな草萌ゆる
母の死は、かれの人生を大きく支配したであろう。
母ようどんそなえてわたしもいただきます
山頭火の句も他者に響くが、彼に他者の愛は響いていたのであろうか。
Posted by okina-ogi at 12:05│Comments(0)
│旅行記